- HOME>
- 内分泌(甲状腺)・代謝内科
内分泌(甲状腺)内科について

内分泌(甲状腺)内科では、内分泌疾患(特に甲状腺疾患)の診断・治療を行っております。
内分泌疾患はホルモン(血液を介して標的となる臓器に作用することにより生命機能を維持する働きをもつ重要な生理活性物質)を作る内分泌臓器(内分泌腺)の障害により、ホルモン分泌の異常(増加または低下)が起こった状態か、またはそのホルモンが作用する対象臓器の異常(ホルモン受容体やホルモン情報伝達の障害)により、ホルモン作用の異常が起こり、さまざまな症状を呈するようになった状態です。内分泌疾患は内分泌腺別に甲状腺疾患、下垂体疾患、副腎疾患、副甲状腺疾患、性腺疾患に分類されます。
内分泌(甲状腺)内科では、内分泌疾患、とりわけ甲状腺疾患の正確で迅速な診断と的確な治療に重点を置いた診療を行っております。甲状腺疾患(バセドウ病・橋本病など)の診断・治療効果判定指標である甲状腺ホルモン(FT3・FT4)・甲状腺刺激ホルモン(TSH)やバセドウ病診断に必須不可欠な血液検査項目である抗TSHレセプター抗体(TRAb)、橋本病診断に不可欠な血液検査項目である抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)、抗サイログロブリン抗体(TgAb)、さまざまな甲状腺疾患のマーカーであるサイログロブリン(Tg)も院内迅速血液検査にて測定可能です。また、甲状腺エコー検査での画像診断も可能です。「首の腫れ・しこりが心配。ひょっとしたら甲状腺の病気かも?」という不安な気持ちを抱えておられるようでしたら、是非お気軽にご相談ください。
内分泌疾患にみられる症状
このような症状がみられる場合、内分泌疾患の可能性もあるため、内分泌代謝科専門医にご相談ください。
症状別内分泌疾患一覧
下記に内分泌疾患にみられる主要症状を列記し、その症状をきたしうる代表的な内分泌疾患についても併せて記載しました。内分泌疾患は、早期発見が非常に重要な疾患です。下記の症状が当てはまる方や、気になることがございましたら、大阪市西区のきよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニックへお気軽にご相談ください。
全身倦怠感
全身倦怠感とは体がだるい・重い、疲れやすいといった身体全体のだるさを指し示す言葉であり、場合によっては、日常生活に支障をきたすこともあります。
代表的な内分泌疾患(全身倦怠感):甲状腺機能低下症、バセドウ病、副腎皮質機能低下症、褐色細胞腫
発熱
発熱とは、視床下部の体温調節中枢の基準点が上昇し、日内変動の正常範囲を超えて体温が高くなった状態であり、37.0℃~37.4℃を「微熱」、37.5℃以上を「発熱」、38.0℃以上を「高熱」といいます。
代表的な内分泌疾患(発熱):バセドウ病、亜急性甲状腺炎、副腎皮質機能低下症、褐色細胞腫
動悸
心臓の拍動を不快感または不安感を伴って感じた状態であり、脈の増減、不整脈、強い心臓の拍動を伴う疾患によって引き起こされます。
代表的な内分泌疾患(動悸):バセドウ病、亜急性甲状腺炎、無痛性甲状腺炎、褐色細胞腫
高血圧
高血圧とは診察室の収縮期血圧が140 mmHg以上または拡張期血圧が90 mmHg以上の状態です。
代表的な内分泌疾患(高血圧):バセドウ病、亜急性甲状腺炎、無痛性甲状腺炎、先端巨大症、クッシング症候群、原発性アルドステロン症、褐色細胞腫
低血圧
低血圧とは診察室の収縮期血圧100 mmHg未満の状態です。
代表的な内分泌疾患(低血圧):下垂体機能低下症、副腎皮質機能低下症
浮腫
浮腫とはむくみのことです。
代表的な内分泌疾患(浮腫):甲状腺機能低下症、バセドウ病、クッシング症候群
肥満
肥満とは体内の脂肪組織が過剰に増加した状態あり、BMI(Body Mass Index:体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)により算出された肥満係数)が25 kg/m2以上を肥満、BMIが35 kg/m2以上を高度肥満といいます。
代表的な内分泌疾患(肥満):クッシング症候群、甲状腺機能低下症、インスリノーマ、多嚢胞性卵巣症候群
体重減少
半年〜1年以内に5%以上の体重減少を臨床上問題とします。
代表的な内分泌疾患(体重減少):バセドウ病、亜急性甲状腺炎、無痛性甲状腺炎、副腎皮質機能低下症、褐色細胞腫
悪心・嘔吐
嘔吐とは胃内容物が不随意に口腔に逆流し、体外に排出される状態であり、悪心とは嘔吐したくなる感覚のことです。
代表的な内分泌疾患(悪心・嘔吐):原発性副甲状腺機能亢進症、急性副腎不全
下痢
下痢とは、水分含量が多い便を頻回に排出する状態のことです。
代表的な内分泌疾患(下痢):バセドウ病、カルチノイド症候群、ガストリノーマ
口渇・多飲
高血糖や高Na血症によって引き起こされる血漿浸透圧の上昇や循環血流量の減少を受容体に感知され、視床下部にある口渇中枢に伝達されることによって口渇(のどが渇くこと)を引き起こし、多飲(水分をたくさん飲むこと)を生じます。口腔内の乾燥によっても口渇・多飲は起こります。
代表的な内分泌疾患(口渇・多飲):中枢性尿崩症、腎性尿崩症、原発性副甲状腺機能亢進症
多毛
多毛とは、女性や小児における男性ホルモン依存性の体毛増加のことです。
代表的な内分泌疾患(多毛):多嚢胞性卵巣症候群、クッシング症候群、先天性副腎皮質過形成
色素沈着
色素沈着とは、皮膚の一部の色調が黒色や茶色などの濃い色に変化した状態のことです。
代表的な内分泌疾患(色素沈着):原発性副腎皮質機能低下症(アジソン病)、クッシング病、先天性副腎皮質過形成
無月経
無月経とは、月経(生理)が一度もこない状態もしくはこれまできていた月経が3ヶ月以上こない状態のことです。
代表的な内分泌疾患(無月経):甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、汎下垂体機能低下症、高プロラクチン血症、クッシング症候群、多嚢胞性卵巣症候群
男性化
男性化とは、女性や小児において男性ホルモンの過剰により多毛、痤瘡(にきび)、月経異常、声の低音化などをきたす状態のことです。
代表的な内分泌疾患(男性化):クッシング症候群、先天性副腎皮質過形成、多嚢胞性卵巣症候群
甲状腺疾患
甲状腺とは
甲状腺は、のどぼとけ(甲状軟骨)のすぐ下にあり、気管を前から取り囲むように位置する蝶のような形をした小さな内分泌臓器です。甲状腺から分泌されるホルモン(甲状腺ホルモン)には体内の代謝を促進する重要な働きがあります。
甲状腺ホルモン
甲状腺ホルモンにはT3(トリヨードサイロニン)とT4(サイロキシン)の2種類あり、これらはTSH(甲状腺刺激ホルモン)の刺激によって甲状腺から分泌されます。甲状腺から最も多く分泌されるホルモンはT4、実際に全身の諸臓器に作用する甲状腺ホルモンはT3で、T3の約80%は肝臓や腎臓でT4から変換されたものです。T3、T4は99%以上を占めるタンパク質と結合している蛋白結合型、ごく僅かに存在するFT3(遊離型トリヨードサイロニン)、FT4(遊離型サイロキシン)といったタンパク質と結合していない遊離型として血中を循環しています。蛋白結合型は細胞内に入ることができず、遊離型のみが細胞内に入り、実際に作用します。そのため、甲状腺の血液検査ではFT3、FT4およびTSHを測定するのが一般的となっています。
甲状腺ホルモン(T3・T4)の濃度が低下すると、下垂体がこれを感知してTSHをより多く分泌します。TSHは甲状腺ホルモンを合成する甲状腺濾胞細胞の細胞膜にあるTSH受容体(レセプター)に結合して、甲状腺ホルモン(T3・T4)の合成・分泌を促進します。逆に、甲状腺ホルモン(T3・T4)の濃度が上昇しすぎると、下垂体が感知してTSHの分泌を減少させることにより甲状腺ホルモン(T3・T4)の濃度を減少させます。このようにして甲状腺ホルモン(T3・T4)は、その濃度を一定に保つように調節されています。
甲状腺疾患とは
甲状腺疾患としては、甲状腺ホルモンが過剰になったり(甲状腺中毒症(広義の甲状腺機能亢進症))、不足したりする(甲状腺機能低下症)ことで体調に変化が起きる病気と甲状腺腫瘍があげられます。
甲状腺中毒症(広義の甲状腺機能亢進症)
甲状腺中毒症とは生体の各組織が過剰な甲状腺ホルモンにさらされる病態のことであり、狭義の甲状腺機能亢進症(以下、甲状腺機能亢進症と記載します)と破壊性甲状腺中毒症に分類されます。
甲状腺機能亢進症とは甲状腺ホルモンが過剰に分泌される疾患の総称であり、代表的疾患としてはバセドウ病があげられます。その他、妊娠一過性甲状腺機能亢進症やTSH産生腫瘍、中毒性単結節性甲状腺腫(プランマー病)などの病気も甲状腺機能亢進症の原因となります。
一方、破壊性甲状腺中毒症とは、何らかの炎症性変化や傷害によって甲状腺組織が破壊されることにより甲状腺に蓄えられていた甲状腺ホルモンが一過性に血中に大量に放出される状態のことであり、一時的に甲状腺機能亢進症に似た症状を呈します。代表的疾患としては、亜急性甲状腺炎、無痛性甲状腺炎といった破壊性甲状腺炎があげられます。その他、放射線治療後の甲状腺中毒症や特定の薬剤(免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬、インターフェロン、アミオダロンなど)による甲状腺中毒症なども破壊性甲状腺中毒症に分類されます。
甲状腺中毒症でみられる症状は以下の通りです。
全身倦怠感、体重減少、暑がり、食欲亢進、軟便、下痢、頻脈(1分あたりの心拍数が100回以上の状態)、動悸、高血圧、手指のふるえ、発汗過多、皮膚湿潤、不眠、いらいら、落ち着きがなくなる、月経異常(無月経、月経過少)、不妊など。
バセドウ病では、前記の症状に加え、甲状腺腫大や眼球突出、脛骨前粘液水腫(足のすねの皮膚の一部が腫れて色が赤黒くなる病気)といった症状もみられます。
甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症とは甲状腺のホルモン産生能が低下することにより様々な症状がみられる疾患の総称であり、病変部位により、原発性(甲状腺性)、中枢性(下垂体性/視床下部性)に分けられます。甲状腺機能低下症の原因の大半は原発性である橋本病(慢性甲状腺炎)です。
甲状腺機能低下症でみられる症状は以下の通りです。
全身倦怠感、体重増加、むくみ、寒がり、食欲低下、便秘、徐脈(1分あたりの心拍数が60回未満の状態)、低血圧、発汗減少、皮膚乾燥、脱毛、傾眠、無気力、月経異常(無月経、月経過多)、不妊など。
甲状腺腫瘍
甲状腺内にできる結節(しこり)を甲状腺結節といい、腫瘍(良性・悪性)、腫瘍様病変に分類されます。甲状腺結節は無症状のことが多いため、頸部のしこりに偶然気づいたり、健診などで指摘されたりする方が増えています。甲状腺腫瘍の多くは良性腫瘍であり、濾胞腺腫などがあげられます。悪性腫瘍(甲状腺がん)は、乳頭がんが全体の90%以上を占めているといわれています。腫瘍様病変は良性結節であり、腺腫様甲状腺腫、甲状腺のう胞などがあげられます。甲状腺内に結節の存在が疑われる場合、甲状腺超音波検査を実施し、結節の有無や大きさ、性状、甲状腺内の位置などを調べます。大きさが1 cmを超える結節の場合、良性・悪性の判断をするための穿刺吸引細胞診検査が必要となりますので、連携先の地域基幹病院をご紹介させていただきます。
甲状腺中毒症(広義の甲状腺機能亢進症)と甲状腺機能低下症の症状の違いについて
| 甲状腺中毒症/広義の甲状腺機能亢進症の症状 | 甲状腺機能低下症の症状 |
|---|---|
| 全身倦怠感 | 全身倦怠感 |
| 体重減少 | 体重増加/むくみ |
| 暑がり | 寒がり |
| 食欲亢進 | 食欲低下 |
| 軟便/下痢 | 便秘 |
| 頻脈/動悸 | 徐脈 |
| 高血圧 | 低血圧 |
| 手指のふるえ | – |
| 発汗過多 | 発汗減少 |
| 皮膚湿潤 | 皮膚乾燥 |
| 脱毛 | 脱毛 |
| 不眠 | 傾眠 |
| いらいら/落ち着きがなくなる | 無気力 |
| 無月経 | 無月経 |
| 月経過少 | 月経過多 |
| 不妊 | 不妊 |
バセドウ病
バセドウ病とはびまん性甲状腺腫(甲状腺全体が大きくなった状態)を伴った甲状腺機能亢進症であり、甲状腺に対する自己抗体である抗TSHレセプター抗体(TRAb)を認める自己免疫疾患(本来なら感染や病気から身体を守る免疫システムに異常が生じ、自身の身体の一部を攻撃してしまう病気)です。
プランマー病
プランマー病とは甲状腺内の結節性病変がTSHの調節を受けずに自律的に甲状腺ホルモンを分泌することにより甲状腺機能亢進症をきたす疾患です。ほとんどが良性結節であり、悪性腫瘍が原因となることは極めて稀です。プランマー病は甲状腺機能亢進症状を呈しますが、バセドウ病のような眼球突出がみられず、この点が症状におけるバセドウ病との鑑別点となります。
診断には血液検査とシンチグラフィ検査が有用です。血液検査ではTSHの低下、FT3、FT4の上昇を認めます。抗TSHレセプター抗体(TRAb)が陰性であることが、バセドウ病との鑑別点となります。シンチグラフィでは結節に一致した集積を認めます(非結節部の取り込みは低下します)。プランマー病は上記の症状および血液検査結果やシンチグラフィなどの画像検査所見などによって診断されます。
治療としては、外科的腫瘍切除術や経皮的エタノール注入療法(PEIT)などが行われます。
プランマー病が疑われる場合、連携先の地域基幹病院をご紹介させていただきます。
亜急性甲状腺炎
亜急性甲状腺炎は原因不明(おそらくウイルス感染)の甲状腺炎で、甲状腺ホルモンを蓄えている濾胞が破壊されることによって一過性に甲状腺ホルモンが高値となる破壊性甲状腺中毒症の一つです。一般に予後は良好で、30〜40歳代の女性に多くみられます。症状としては、前駆症状としての上気道炎ののち、自発痛、圧痛を伴う甲状腺腫(甲状腺が大きくなった状態)を認め、痛みは耳介後部へ放散します。その他、高熱、全身倦怠感、動悸、発汗過多、手指のふるえ、体重減少も認めます。
診断には血液検査と超音波検査が有用です。血液検査ではTSHの低下、FT3、FT4の上昇を認めます。抗TSHレセプター抗体(TRAb)が陰性であることが、バセドウ病との鑑別点であり、炎症マーカー(白血球数、CRP)が陽性であることが、無痛性甲状腺炎との鑑別点となります。超音波検査では疼痛部に一致した境界不明瞭な低エコー域を認めます。亜急性甲状腺炎は上記の症状および血液検査結果や超音波検査などの画像検査所見などによって診断されます。
治療としては、軽症例では、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、炎症が強いときには、副腎皮質ステロイドが使用されます。頻脈に対してβ遮断薬が使用されます。副腎皮質ステロイドで治療している場合、症状が改善したら徐々に薬を減量し、中止としますが、減量中に症状が再燃することもありますので、その場合は、早めにご受診ください。症状が改善したからといって、急に副腎皮質ステロイドの内服を自己中断すると、症状が再燃する場合がありますので、薬を切らさないように定期受診を心掛けてください。通常、数ヶ月で症状は消失し、甲状腺ホルモンも正常化しますが、その後一過性の甲状腺機能低下症、一部に永続的な甲状腺機能低下症となることもありますので、副腎皮質ステロイドの内服終了後も、甲状腺機能の経過を血液検査でしばらくは確認する必要があります。また、亜急性甲状腺炎の再発は稀ですが、10年以上経過してから再発することもあります。
無痛性甲状腺炎
無痛性甲状腺炎は橋本病(慢性甲状腺炎)を基礎として発症することが多く、甲状腺ホルモンを蓄えている濾胞が破壊されることによって一過性に甲状腺ホルモンが高値となる破壊性甲状腺中毒症の一つです。散発性に自然発症するものと出産後に発症するもの(出産後甲状腺炎)とがあります。無痛性甲状腺炎の発症には自己免疫機序が関与していると言われており、出産や副腎皮質ステロイド内服の急速な中止、インターフェロンや分子標的薬などの薬剤投与など原因はさまざまです。橋本病を基礎にもつ20〜40歳代の女性に多くみられ、症状としては、動悸、頻脈、発汗過多、手指のふるえ、全身倦怠感、体重減少などをきたします。発熱を認めず、甲状腺に自発痛・圧痛がないことが、亜急性甲状腺炎との症状における鑑別点となります。
診断には血液検査と超音波検査が有用です。血液検査ではTSHの低下、FT3、FT4の上昇を認めます。抗TSHレセプター抗体(TRAb)が陰性であることが、バセドウ病との鑑別点となりますが、無痛性甲状腺炎の約3%で抗TSHレセプター抗体(TRAb)が陽性となることもあり、抗TSHレセプター抗体(TRAb)が軽度高値(2.0〜3.0 IU/L)の場合には特に注意が必要です。また、炎症マーカー(白血球数、CRP)が陰性であることが、亜急性甲状腺炎との鑑別点となります。その他、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPOAb)、抗サイログロブリン抗体(TgAb)が陽性となります。
超音波検査では炎症部位が無血流の低エコー領域として検出されますが、非常に軽症の場合、何の変化もないこともあります。無痛性甲状腺炎は上記の症状および血液検査結果や超音波検査などの画像検査所見などによって診断されます。
治療としては、頻脈に対してβ遮断薬が使用されることもありますが、基本的には経過観察となります。無痛性甲状腺炎にみられる甲状腺中毒症状は3ヶ月以内に消失し、その後は甲状腺機能が一過性に低下した後に正常化しますが、甲状腺機能が正常化せず永続性の甲状腺機能低下症に移行することもあります。無痛性甲状腺炎は亜急性甲状腺炎とちがって、再発を繰り返すこともあるため、甲状腺機能が正常化した後も、甲状腺機能の経過を血液検査でしばらく確認する必要があります。
橋本病(慢性甲状腺炎)
橋本病(慢性甲状腺炎)は自己免疫機序(本来なら感染や病気から身体を守る免疫システムに異常が生じ、自身の身体の一部を攻撃してしまうメカニズム)により甲状腺に慢性的な炎症が生じる病気であり、慢性炎症により甲状腺が徐々に破壊されると、甲状腺機能低下症をきたす場合があります。
下垂体疾患
脳の中心に垂れ下がっているように見える下垂体は、径1 cmの小さな内分泌臓器です。下垂体は前葉と後葉に分かれ、前葉からは副腎皮質ホルモン、甲状腺ホルモン、性腺ホルモンのそれぞれの分泌を促すホルモンや成長ホルモン、乳汁分泌ホルモン(プロラクチン)が分泌され、後葉からは抗利尿ホルモンが分泌されます。下垂体ホルモンの分泌に過不足があると、さまざまな体調の異常が現れてきます。
下垂体のホルモン分泌が増加する疾患には先端巨大症、クッシング病、プロラクチノーマなどがあります。逆にホルモン分泌が低下する病気には下垂体機能低下症や中枢性尿崩症などがあります。また、下垂体腫瘍は症状としては視力・視野障害があり、良性が多く、時間をかけてゆっくり増大する特徴があります。
副腎疾患
副腎は腎臓の上にある小さな器官であり、ホルモンを作る働きをしています。副腎に腫瘍ができ、ホルモンが過剰に産生されると、太ってきたり、高血圧になったり、糖尿病になるなど様々な症状が起きてきます。副腎ホルモンは人にとって必要不可欠な物質であり、副腎の働きが悪くなる病気は生命に関わることもあります。血液検査のほか、ホルモン負荷試験や各種画像診断等で正確に診断することが重要です。代表的な副腎疾患としては、原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫、副腎偶発腫瘍、副腎皮質機能低下症などがあげられます。
副甲状腺疾患
副甲状腺疾患の多くは、副甲状腺機能亢進症です。副甲状腺ホルモンの過剰な分泌によって、血液中のカルシウム濃度が上昇し、尿路結石、骨粗鬆症や高カルシウム血症による様々な症状(食欲不振、悪心、嘔吐、便秘、全身倦怠感、のどの渇き、多飲、多尿、精神症状など)を引き起こします。血液中・尿中のカルシウムと副甲状腺ホルモン(PTH)が高値になることで診断ができます。
内分泌性高血圧
日本人の高血圧症の約8~9割が本態性高血圧症(原因をひとつに定めることのできない高血圧症)といわれていますが、なかには別の病気があるために血圧が高くなる二次性高血圧症があります。その多くは内分泌疾患や腎臓病によるものです。とくに治療困難な高血圧症の中には、内分泌性高血圧症が潜んでいる可能性が高く、糖尿病を合併することもあります。このような場合、もとにある内分泌疾患を早めに治療することで、高血圧症や糖尿病が治癒することもあります。
内分泌性高血圧の原因疾患
・甲状腺疾患:バセドウ病
・下垂体疾患:先端巨大症、クッシング病
・副腎疾患:原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫
・副甲状腺疾患:副甲状腺機能亢進症
代謝内科について
代謝内科では、代謝疾患の診断・治療を行っております。
代謝疾患は糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分類され、代表的な疾患としては、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、肥満症、骨粗鬆症などがあげられます。
主な代謝疾患
糖尿病
糖尿病とは膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが、十分に働かないために血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高くなる病気です。大きく1型糖尿病と2型糖尿病に分かれており、日本人で圧倒的に多く、生活習慣病の一つとされているのが2型糖尿病です。その発症には、インスリンの分泌不足といった要因に加え、過食、運動不足、肥満、ストレスといった生活習慣が関係しているといわれています。
糖尿病を発症し進行すると、網膜症、腎症、神経障害など様々な合併症を引き起こすことがあります。糖尿病を予防するため、あるいは進行を遅らせるために生活習慣を見直すことが大切です。当院では諸検査の結果に基づき、患者さま一人ひとりのライフスタイルに応じたきめ細かな治療を行っています。
脂質異常症
脂質異常症とは血液中の「悪玉」と呼ばれるLDLコレステロールや中性脂肪(トリグリセリド)が増えたり、「善玉」のHDLコレステロールが減ったりした状態のことをいいます。この状態を放置していると動脈硬化が起こり、ゆっくり進行し、脳梗塞や心筋梗塞といった動脈硬化性疾患をまねくリスクが高まります。
脂質異常症の発症には、過食、運動不足、肥満、喫煙、過度な飲酒、ストレスなどが関係しているといわれています。また、遺伝性の「家族性高コレステロール血症」と呼ばれているものもあります。
脂質異常症の治療は通常、食事療法と運動療法からはじめます。薬物療法は、これらを行っても脂質管理の目標値が達成できなかったり、持っている動脈硬化の危険因子が多く、動脈硬化や動脈硬化による疾患を起こすリスクが高かったりする場合に開始されます。
高尿酸血症
高尿酸血症とは、血液中の尿酸の濃度(尿酸値)が通常よりも高い状態のことです。高尿酸血症には、尿酸の排泄がうまくいかないタイプ・体内で尿酸をつくりすぎるタイプ・両者の混合型の3つがあり、日本人には排泄がうまくいかないタイプが多いとされています。女性ホルモンには腎臓からの尿酸の排泄を促す作用があるため、明らかな性差が認められ患者さまの大半が男性です。
尿酸が過剰になると、体内で析出して結晶を作り、痛風と呼ばれる病気を発症することがあります。尿酸の結晶は足の親指の付け根に形成されることが多く、激烈な痛みや発赤、腫れなどの痛風関節炎(痛風発作)を引き起こします。そのほか、腎臓にも結晶を作ることもあり、腎臓結石の原因にもなります。高尿酸血症は、アルコールや肉を多く摂取する、といった生活習慣と密接に関連していると考えられています。こうした生活スタイルは、糖尿病や高血圧、脂質異常症、肥満などとも関連しており、動脈硬化を進行させないという観点からも治療を行う必要があります。
肥満症
肥満に伴って糖尿病、高血圧症、脂質異常症などを合併し、減量が必要とされる病態が肥満症です。単純性肥満と内分泌疾患などに伴う二次性肥満があり、単純性肥満でも内臓脂肪の蓄積による内臓脂肪型肥満は、メタボリックシンドローム(腹囲 85 cm以上(男性)/90 cm以上(女性)に加え、脂質代謝異常・高血圧・高血糖のうち2つ以上を併発している状態)の基盤となり、他の生活習慣病や動脈硬化性疾患の危険性が高まるといわれています。重度の肥満症では生活指導とあわせて、薬物療法などが行われることがあります。
骨粗鬆症
骨粗鬆症は、骨の代謝バランスが崩れ、骨形成よりも骨破壊が上回る状態が続き、骨の量と質の低下により骨折しやすくなる病気です。高齢化と共に増加し、予防や早期診断が注目されています。骨粗鬆症には骨芽細胞を活発にする女性ホルモン(エストロゲン)の低下(閉経後骨粗鬆症)などが引き金となって発症する原発性骨粗鬆症のほか、内分泌疾患(副甲状腺機能亢進症など)や糖尿病、薬剤の使用(ステロイドなど)と関係して起こってくる続発性骨粗鬆症があります。
糖尿病・内分泌(甲状腺)のご相談は大阪市西区のきよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニックへ
大阪市中央区や西区で糖尿病や甲状腺疾患についてご相談をお考えの方は、淀屋橋駅から徒歩圏内、肥後橋駅すぐの「きよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニック」にお問い合わせください。専門医による診療とアクセスの良さが特徴です。
当院では、糖尿病・内分泌疾患を専門とする医師による診療が行われており、糖尿病や甲状腺疾患をはじめとするさまざまな内分泌・代謝疾患の診断と治療に対応しています。特に甲状腺の異常や糖尿病に関連する検査に対応するための設備を整えております。まず初めに、糖尿病・内分泌領域の専門医が詳細な問診や診察をさせていただきます。その後、当院導入の大型血液検査装置や超音波検査装置、CT検査装置設備などを活用し、患者さまの症状に応じた適切な検査を受けていただくことが可能です。検査の結果は患者さまに丁寧に説明させていただき、その結果に基づいて、できるかぎり患者さまの意向に沿った治療方針をご提案いたします。
また、夜間診療も実施しており、仕事帰りにも通院しやすい診療体制を整え、患者さまの健康状態やご要望に合わせた診療を心がけております。予約は電話やオンラインから可能です。予約をご利用いただくことで、診療がより円滑に進められます。大阪市で内科診療をご希望の方は、「きよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニック」にご相談ください。尚、診療内容の詳細については直接お問い合わせください。
監修者情報
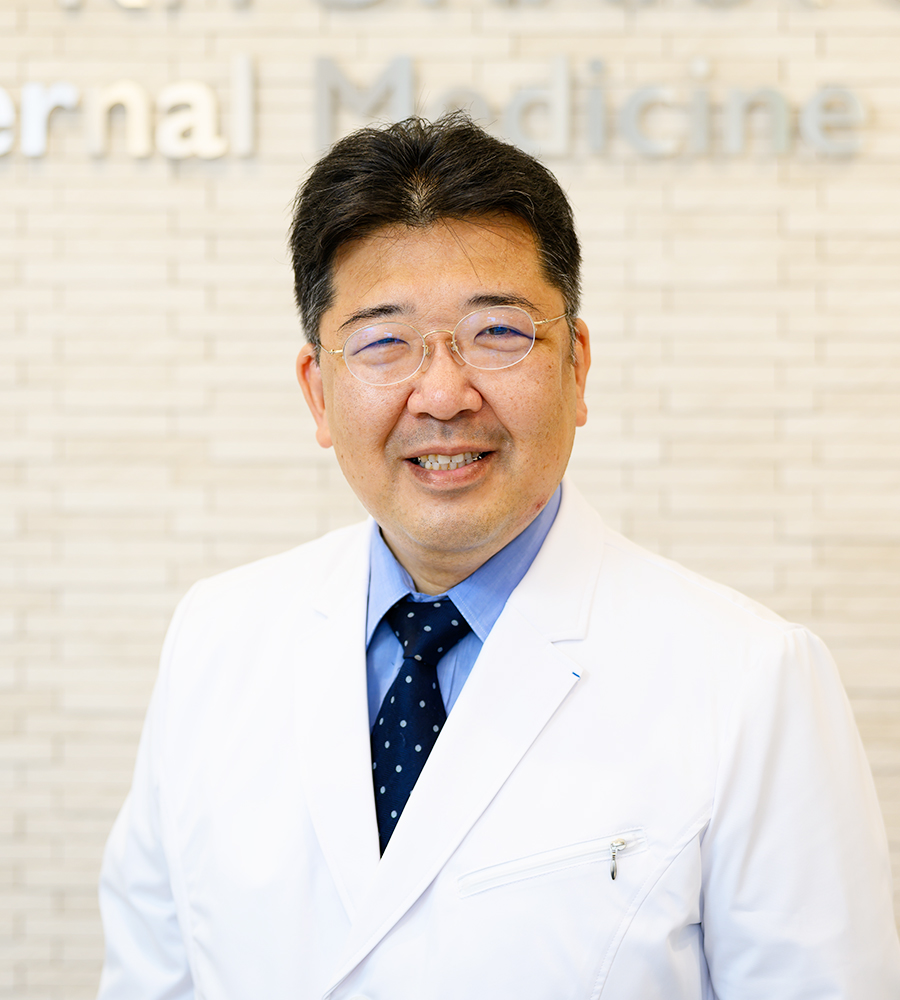
清原 義幹(きよはら よしもと)
きよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニック 院長
経歴
- 1997年神戸大学医学部附属病院 内科系 研修医
- 1998年京都大学大学院医学研究科 博士課程入学
- 2003年京都大学大学院医学研究科 博士課程修了
- 2003年独立行政法人理化学研究所 研究員
- 2007年INSERM フランス国立医学研究機構 研究員
- 2008年医療法人浩仁会 南堺病院 内科 医員
- 2010年医療法人浩仁会 南堺病院 内科 医長
- 2012年独立行政法人労働者健康福祉機構 大阪労災病院 糖尿病内科 医長
- 2016年独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 糖尿病内科 医長
- 2018年独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 糖尿病内科 副部長
- 2019年医療法人浩仁会 南堺病院 糖尿病内科 部長
- 2024年きよはら内科クリニック(現:きよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニック) 院長
ご挨拶
大阪市西区・肥後橋のきよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニックの清原義幹です。当院は糖尿病内科、内分泌 (甲状腺)・代謝内科を中心とした内科専門クリニックです。総合内科・糖尿病・内分泌代謝科の専門医としての知識と経験を活かしつつ、一般内科全般から糖尿病や甲状腺疾患をはじめとする内分泌疾患、高尿酸血症(痛風)などの代謝疾患、健康診断、予防接種まで幅広く診療しております。些細なことであっても、お身体のことでお困りのことがございましたら、是非お気軽にご相談ください。
