- HOME>
- 一般内科
一般内科について

一般内科では、かぜやインフルエンザ、肺炎といった日常生活の中で比較的遭遇しやすい急性疾患から、気管支喘息や逆流性食道炎、蕁麻疹(じんましん)や花粉症などのアレルギー疾患、生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症など)といった慢性疾患の継続的な治療とコントロールを行っております。また、患者様の中には、体の不調は自覚しているのに、どの科を受診すればよいのか分からず、お困りになられた経験のある方もいらっしゃるかと思います。そのようなときにこそ、まずは一般内科を受診していただければ、お困りの症状が体のどのような不調で起こっているのかを判断し、必要に応じて検査を行った上で適切な治療法をご提案いたします。専門的な高度医療が必要な場合は、速やかに連携先の地域基幹病院へご紹介させていただきます。
一般内科の症状と疾患
- 発熱や咳、痰、鼻水、のどの痛みなど
- 呼吸がゼーゼーする、息苦しい、咳が長く続く
- 頭痛やめまい、立ちくらみがする
- 胸が痛い、動悸がする、息切れしやすい
- 腹痛、下痢、便秘、お腹の調子が悪い
- 吐き気、嘔吐、胃のムカムカ、お腹の張り
- 食欲がない、最近疲れやすい、体重が減ってきた
- 花粉症、蕁麻疹、喘息などのアレルギー
- トイレが近い、排尿時の痛み、血が混ざる
- 湿疹がでる、皮膚が乾燥してかゆい
- 夜眠れない
- 足がむくむ
日常的に起こりやすい症状でも、適切な検査を行うことで重大な病気の早期発見につながることもよくあります。当院では原則予約なしでCT検査での精査を受けていただくことができます。同時に血液・尿検査や心電図検査、超音波検査(予約が必要な場合があります)を受けていただくことができ、各種検査結果は原則、診療時間内にご説明させていただきます。
体調不良や健康に関して気になることがございましたら、何でもお気軽にご相談ください。
一般内科の主な病気
風邪(感冒)

風邪(かぜ)は医学的には「風邪(かぜ)症候群」、「感冒」と呼ばれ、のどの痛みや鼻症状(くしゃみ、鼻水、鼻づまり)、咳、痰などを主症状とする上気道(鼻やのど)の急性炎症の総称です。発熱、頭痛、全身の倦怠感(だるさ)、食欲低下などを伴う場合がありますが、発熱はあっても微熱程度で、頭痛や倦怠感などの全身症状も軽いという特徴があります。一般的に原因微生物の80~90%はウイルスが占めており、口や鼻から侵入し、気道粘膜から感染して炎症を引き起こします。風邪は通常、症状を自覚するようになってから1週間程度で軽快します。症状が1週間以上も持続している場合や「高熱が出る」、「咳が止まらない」など、症状が悪化している場合には、二次性の細菌感染症(肺炎など)を発症している可能性がありますので、ご来院の上、血液検査やX線検査・CT検査を受けられることをおすすめします。
扁桃炎(扁桃腺炎)
扁桃炎とは、のどの奥の左右両側にある扁桃と呼ばれる部位に細菌やウイルスが感染し、炎症を起こす病気のことです。扁桃が赤く腫れ、白い膿(白苔)を持つこともあります。扁桃炎の症状には、のどの痛み(特に物を飲み込むときの強い痛み)、発熱、あごの下(顎下)や首(頸部)のリンパ節の腫れなどがあります。扁桃炎の治療としては、抗生物質(細菌性の場合)、消炎鎮痛剤、解熱剤などを内服していただくことになります。炎症がひどい場合には抗生剤の点滴を受けていただくこともありますので、高熱やのどの強い痛みがあらわれた場合には、お早めにご来院ください。
肺炎
肺炎とは、気道より肺に侵入した細菌やウイルスなどの病原体が増殖し、肺に炎症を引き起こした状態のことをいいます。死亡原因に占める順位は全体で5位ですが、高齢者で多くなっています。肺炎の症状としては、発熱、咳、痰が主な症状となりますが、重症化すれば呼吸困難、炎症が胸膜まで広がれば胸痛を伴います。これらの症状を放置した場合は、肺から全身に細菌などの病原体がまわり敗血症といった重篤な状態となることがありますので、お早めにご来院の上、血液検査やX線検査・CT検査を受けられることをおすすめします。肺炎の治療としては、細菌性の場合は抗生物質などを内服していただくことになります。炎症がひどい場合には抗生剤の点滴を受けていただくこともあります。「高熱が出る」、「咳が止まらない」、「息苦しい」、「胸が痛い」などの症状があらわれた場合には、お早めにご来院ください。
気管支喘息
気管支喘息は空気の通り道(気道)に炎症が続き、さまざまな刺激に気道が敏感になって発作的に気道が狭くなることを繰り返す病気です。日本では子供の8~14%、大人では9~10%の方が喘息に罹患しています。高年齢で発症する方もおられます。炎症の原因はチリダニやハウスダスト、ペットのフケ、カビなどのアレルギーによることが多いのですが、その原因物質が特定できないこともあります。
発作的に咳や痰が出て、ゼーゼー、ヒューヒューという音を伴って息苦しくなります(喘息発作と呼びます)。夜間や早朝に出やすいのが特徴です。
このような症状を繰り返していれば、喘息の可能性があります。呼吸機能検査で気道の空気の流れが悪くなっていないかどうか調べます。気管支拡張薬を吸ったあとにその流れが改善すれば喘息の可能性が高いです。また、痰の検査をしたり、血液検査でアレルギー体質かどうかなども検査します。
症状が無ければ喘息は治ったと思われるかもしれませんが、気道の炎症は続いています。炎症が続けばいずれまた発作が起こり、学校や会社を休んだり、日常・社会生活に影響が出ます。そして炎症が続くと気道が固く狭くなり元に戻らなくなりますので、治療によって症状をおさえることが困難になります。したがって、日頃から炎症をおさえる薬を使って発作を予防しなければなりません。その主役は吸入ステロイド薬(ICS)です。適切に使用すれば副作用は少なく安全です。喘息の重症度に応じて吸入ステロイド薬(ICS)の量を調整したり、気管支拡張薬である長時間作用型β2刺激薬(LABA)や長時間作用型抗コリン薬(LAMA)を必要に応じて併用します。長時間作用型抗コリン薬(LAMA)には咳や痰の症状を改善する効果があることが知られており、吸入ステロイド(ICS)と長時間作用型β2刺激薬(LABA)の2剤配合剤(ICS/LABA)だけでなく、長時間作用型抗コリン薬(LAMA)を含めた3剤配合剤(ICS/LABA/LAMA)も喘息治療薬として広く使用されるようになっています。炎症を抑え、鼻づまりを改善する効果もあるロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)も適宜併用されます。また、アレルギーの原因が分かっている場合はそれらを避け、喫煙していれば禁煙しましょう。もし発作が起こったら、即効性のある気管支拡張薬である短時間作用型β2刺激薬(SABA)を吸入しましょう。何度か繰り返しても改善しなければ速やかに病院を受診してください。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)
慢性閉塞性肺疾患(COPD:chronic obstructive pulmonary disease)とは、従来、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称です。タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露することで生じた肺の炎症性疾患であり、喫煙習慣を背景に中高年に発症する生活習慣病といえます。
最大の原因は喫煙であり、喫煙者の15~20%がCOPDを発症します。タバコの煙を吸入することで肺の中の気管支に炎症がおきて、せきやたんが出たり、気管支が細くなることによって空気の流れが低下します。また、気管支が枝分かれした奥にあるぶどうの房状の小さな袋である肺胞(はいほう)が破壊されて、肺気腫という状態になると、酸素の取り込みや二酸化炭素を排出する機能が低下します。COPDではこれらの変化が併存していると考えられており、治療によっても元に戻ることはありません。
歩行時や階段昇降など、身体を動かした時に息切れを感じる労作時呼吸困難や慢性のせきやたんが特徴的な症状です。一部の患者では、喘鳴や発作性呼吸困難などぜんそくの様な症状を合併する場合もあります。
長期の喫煙歴があり慢性にせき、たん、労作時呼吸困難があればCOPDが疑われます。確定診断にはスパイロメトリーといわれる呼吸機能検査が必要です。1秒率という指標が70%未満であり、閉塞性障害をきたすその他の疾患を除外できればCOPDと診断されます。
喫煙を続けると呼吸機能の悪化が加速してしまいますので、禁煙が治療の基本となります。増悪をさけるためには、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種が勧められます。薬物療法の中心は気管支拡張薬(抗コリン薬・β2刺激薬・テオフィリン薬)です。効果や副作用の面から吸入薬が推奨されており、主として長時間気管支を拡張する長時間作用型抗コリン薬(LAMA)や長時間作用型β2刺激薬(LABA)が使用されています。気流閉塞が重症で増悪を繰り返す場合は、吸入ステロイド薬(ICS)を使用します。また重症度に応じて長時間作用型β2刺激薬(LABA)と長時間作用型抗コリン薬(LAMA)の2剤配合剤(LABA/LAMA)や吸入ステロイド薬(ICS)を含めた3剤配合剤(ICS/LABA/LAMA)も適宜使用されます。非薬物療法では呼吸リハビリテーション(口すぼめ呼吸や腹式呼吸などの呼吸訓練・運動療法・栄養療法など)が中心となります。低酸素血症が進行してしまった場合には在宅酸素療法が導入されます。さらに呼吸不全が進行した場合は、小型の人工呼吸器とマスクを用いて呼吸を助ける換気補助療法が行われることもあります。症例によっては過膨張した肺を切除する外科手術(肺容量減少術)が検討されることもあります。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に無呼吸を繰り返すことで、様々な合併症を起こす病気です。 空気の通り道である上気道が狭くなることが原因です。首まわりの脂肪の沈着が多いと上気道は狭くなりやすく、肥満は睡眠時無呼吸症候群と深く関係しています。扁桃肥大、舌が大きいことや、鼻炎・鼻中隔弯曲といった鼻の病気も原因となります。あごが後退していたり、あごが小さいことも睡眠時無呼吸症候群の原因となり、肥満でなくても睡眠時無呼吸症候群になります。 いびき、夜間の頻尿、日中の眠気や起床時の頭痛などを認めます。日中の眠気は、作業効率の低下、居眠り運転事故や労働災害の原因にもなります。
問診などで睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は、精密検査である終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)や携帯型装置による簡易検査(簡易PSG)にて睡眠中の呼吸状態の評価を行います。PSGにて、1時間あたりの無呼吸と低呼吸を合わせた回数である無呼吸低呼吸指数(AHI)が5以上であり、かつ上記の症状を伴う際に睡眠時無呼吸症候群と診断します。その重症度はAHIが5以上15未満を軽症、15以上30未満を中等症、30以上を重症としています。簡易PSGでは睡眠時無呼吸症候群の重症度の指標として呼吸障害指数(RDI)または呼吸イベント指数(REI)が用いられ、AHIに近似した数値として扱われます。つまりRDIまたはREIが5以上15未満を軽症、15以上30未満を中等症、30以上を重症として便宜的に分類されます。
精密検査(PSG)でAHIが20以上もしくは簡易検査(簡易PSG)でRDIまたはREIが40以上であって日中の眠気などを認める睡眠時無呼吸症候群では、経鼻的持続陽圧呼吸療法(Continuous positive airway pressure:CPAP)が標準的治療とされています。CPAPはマスクを介して持続的に空気を送ることで、狭くなっている気道を広げる治療法です。また、下あごを前方に移動させる口腔内装置(マウスピース)を使用して治療することもあります。小児のSASではアデノイド・口蓋扁桃肥大が原因であることが多く、その際はアデノイド・口蓋扁桃摘出術が有効です。
肥満者では減量することで無呼吸の程度が軽減することが多く、食生活や運動などの生活習慣の改善を心がけることが重要です。アルコールは睡眠の質を悪化させるので、晩酌は控える必要があります。
成人の睡眠時無呼吸症候群では高血圧、脳卒中、心筋梗塞などを引き起こす危険性が約3~4倍高くなり、特に、AHI 30以上の重症例では心血管系疾患発症の危険性が約5倍にもなります。しかし、CPAP治療にて、健常人と同等まで死亡率を低下させることが明らかになっています。
不整脈
不整脈とは、一連の心拍が不規則、速すぎる(頻脈)、遅すぎる(徐脈)、あるいは心臓内で電気刺激が異常な経路で伝わるなど、心拍リズムの異常のことをいいます。
通常心臓は1分間約60~80回の規則的なリズムで拍動を繰り返していますが、このリズムは右心房にある洞結節という場所で作られます。ここで発生するごく微量の電気が「刺激伝導系」という経路をつたって心房から心室に伝達されて心臓の拍動を生じ、血液が全身に送り出されます。この「刺激伝導系」はいわば天井裏を張っている電線のようなものだと考えればよく、その途中の心房と心室の間には房室結節とよばれるいわば変電所のようなところがあって電気が心室に伝わるのを調節しており、最も効率的な収縮を得るために心房の収縮のあとわずかな時間差をおいて心室の収縮が起こるようになっています。
健康成人で不整脈がまったくない人はいないといってもよいほど、不整脈は一般的なものです。不整脈がありながら自分ではまったく気づかず、身体検査ではじめて不整脈を指摘される人も少なくありません。不整脈を指摘されたときに、脈の不整や激しい動悸を感じる場合は医療機関を受診しましょう。それがどんな不整脈なのか、そのまま放置しておいてよいものなのか、危険な不整脈に発展することがないか、治療を要する不整脈なのか、などをよく聞いて適切な指導をうけることが大切です。治療しなくてもよいものもたくさんありますが、不整脈によっては心不全や失神発作を起こしたり、脳梗塞を併発したりするものもあり、早期の治療が必要な場合があることを念頭においてください。
慢性心不全
心臓は全身に血液を送り出すポンプの働きをしています。心不全というのは病名ではなく、さまざまな心臓の病気の結果、このポンプの働きに障害が生じていろいろな症状を引き起こしている状態を指すものです。
心臓を養っている血管が詰まって血液が流れなくなり心筋が死んでしまう心筋梗塞や、突然発症した不整脈などによって急激にポンプの働きが弱まり短期間に悪化する場合が急性心不全です。
一方、心筋症、高血圧や弁膜症などが原因で長年にわたって心不全症状を認める場合を慢性心不全といいます。
慢性心不全は高血圧、脂質異常症(高コレステロール血症など)、 糖尿病などの生活習慣病との関連性が高く、高齢になるほど発症する人が多くなります。日本では、65歳以上の高齢者の占める比率が増加の一途をたどっていますので、これからますます慢性心不全をもつ人が増えると思われます。
逆流性食道炎
逆流性食道炎とは、胃と食道のつなぎ目にある下部食道括約筋がゆるんでしまうことにより、胃酸が食道に逆流してしまい、防御機能のない食道で炎症を起こし、胸焼けや呑酸などの不快な症状を起こす病気です。胸焼けや呑酸の他、食後や横になったときに出る乾いた咳も逆流性食道炎の症状の一つです。実際に長引く咳(慢性咳嗽)の原因疾患の1割程度が逆流性食道炎であるとも言われています。
逆流性食道炎の治療としては、まずは、「アルコールや喫煙を控える」、「食後最低でも1時間は横にならない」などの生活習慣や食習慣の改善となります。生活習慣・食習慣の改善を試みても症状が軽減しない場合や、症状が強く早期の症状改善が必要な場合はお薬による治療を行います。治療薬として、胃酸分泌抑制薬(ヒスタミンH2受容体拮抗薬、プロトンポンプ阻害薬、カリウムイオン競合型アシッドブロッカー)や制酸薬/粘膜保護薬、消化管運動機能改善薬などが使用されます。
胃・十二指腸潰瘍
胃・十二指腸の壁は、内側から順番に粘膜層、粘膜筋板、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜という6層からなりますが、この壁が胃酸などにより粘膜筋板を越えて深く組織欠損を起こした状態のことを胃・十二指腸潰瘍といいます。一般に、若年者では十二指腸潰瘍の割合が多いのに対して、高齢者では胃潰瘍の割合が多くなります。
症状としては、心窩部痛(みぞおちあたりの痛み)、悪心、嘔吐などの他、合併症として、吐血(コーヒー残渣様)、下血(黒色便)、消化管穿孔などが生じることがあります。ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の感染や非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の使用が胃・十二指腸潰瘍の発生リスクになると考えられており、ピロリ菌感染が確認された場合は除菌療法を行い、可能な限りNSAIDsの内服を中止します。診断には上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)が有用で、治療としては、胃酸分泌抑制薬(ヒスタミンH2受容体拮抗薬、プロトンポンプ阻害薬、カリウムイオン競合型アシッドブロッカー)や選択的ムスカリン受容体拮抗薬、粘膜保護薬などによる内服治療の他、潰瘍よりの出血が持続している場合には、内視鏡的止血術が実施されることもあります。
慢性胃炎
慢性胃炎とは、長期間にわたり胃の粘膜に炎症が持続することにより胃酸などを分泌する胃底腺が萎縮し、胃酸の分泌が低下する病気のことです。
症状としては心窩部痛(みぞおちあたりの痛み)、腹部膨満感、悪心、嘔吐、食思不振などを認めることがありますが、慢性胃炎と診断された人の約半数は無症状と言われています。原因としてはヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)感染が約80%と圧倒的で、その他、自己免疫性、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などがあげられます。診断には上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)が有用で、治療薬としては、自覚症状がある場合には、胃酸分泌抑制薬(ヒスタミンH2受容体拮抗)や粘膜保護薬、消化管運動機能改善薬、抗不安薬などが使用されます。また、胃カメラなどでピロリ菌感染胃炎の確定診断がなされた場合、ピロリ菌の除菌療法が実施されます。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアとは、胃内視鏡検査等の検査で症状の原因となるような器質的な異常を認めないにもかかわらず、慢性的な胃もたれや心窩部痛(みぞおちあたりの痛み)などの上腹部を中心とする腹部症状を呈する疾患のことです。健診受診者の約15%に認められるとの報告もあり、頻度の高い病気と言えます。機能性ディスペプシアには胃の運動機能障害、消化管の知覚過敏、心理・社会的因子、胃酸、食事因子などの数多くの原因が存在し、互いに複雑に影響し発症に関与していると考えられています。
症状としては、食後のもたれ感や早期飽満感(すぐにお腹がいっぱいになる)、心窩部痛、心窩部灼熱感(みぞおちあたりの焼ける感じ)などがあげられます。診断は上記の症状に関する詳細な問診と上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)等の検査により症状の原因となる器質的疾患を除外することにより行われます。治療薬としては、胃酸分泌抑制薬(ヒスタミンH2受容体拮抗薬、プロトンポンプ阻害薬)や消化管運動機能改善薬、漢方薬(六君子湯)などが使用されます。
胃腸炎
胃腸炎とは胃や腸(小腸・大腸)の粘膜に炎症が生じる病気のことであり、病因別に感染性と非感染性に、経過別に急性と慢性に分類されます。
感染性胃腸炎は、ウイルス(ノロウイルスやロタウイルスなど)や細菌(カンピロバクター、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌など)、寄生虫などに感染することにより発症する胃腸炎のことです。感染経路としては、病原体が付着した手で口を触ることによる感染(接触感染)や病原体が付着した食品を摂取することによる感染(経口感染)、感染者の嘔吐物が乾燥し、そこからウイルスが空気中に飛散し、そのウイルスを吸い込むことによる感染(空気感染)があげられ、冬場、幼稚園や小学校、高齢者施設などで集団発生することも少なくありません。症状としては下痢、嘔吐、腹痛、発熱などがあげられ、診断としては、問診と腹部の診察によって行われ、便培養、血液検査などで原因精査を行います。治療としては、充分な水分補給と消化に良い食事を心掛けることにより脱水を予防しつつ、整腸剤や解熱剤、その他、細菌性の場合は抗生剤が使用されます。
一方、非感染性胃腸炎は薬剤性やアレルギー性などの感染以外の原因で発症する胃腸炎のことであり、感染性胃腸炎に比べて、症状は軽症で発熱を認めることはあまりありません。
また、急性胃腸炎は、ほとんどが感染性胃腸炎であり、原因別にウイルス性、細菌性、寄生虫性などに分けられ、下痢、嘔吐、腹痛、発熱などの症状を認めるのに対して、慢性胃腸炎においては感染性、非感染性のどちらも認められ、持続的な下痢、腹痛などの症状がみられます。
腸閉塞/イレウス
腸閉塞/イレウスとは種々の原因により腸内容物の肛門側への輸送が障害された状態のことであり、腸管内腔が物理的に閉鎖されておこる腸閉塞(従来の機械的イレウス)と腸管への血流や分布する神経の障害により腸内容物が停滞するイレウス(従来の機能的イレウス)に大別されます。腸閉塞はさらに腸管への血流障害を伴わない単純性腸閉塞と血流障害を伴う複雑性(絞扼性)腸閉塞に分けられ、イレウスは腸管への血流や神経が障害され、腸管の正常な運動が停止する麻痺性イレウスと腹部打撲などで腸管のけいれんが起こる痙攣性イレウスに分かれます。単純性腸閉塞の原因としては開腹手術や腸管の炎症(憩室炎など)による癒着性のものが最も多く、癒着以外には腫瘍や炎症による狭窄・閉塞があります。複雑性(絞扼性)腸閉塞の原因としては、腸軸捻転症(腸間膜を中心として腸管がねじれる病態)や嵌頓ヘルニア(腸管の一部がヘルニア門(体壁のある部分が弱くなりできた小さな隙間)に挟まり込んで、お腹の中に戻らなくなった状態)などがあげられます。
症状としては腹痛、悪心・嘔吐、便秘、腹部膨満感、発熱、頻脈などがみられます。診断には腹部CT検査が有用です。問診や腹部の診察にて腸閉塞/イレウスが疑われた場合、血液検査にて炎症反応や脱水の有無を確認するとともに、腹部CT検査を実施します。腹部CT検査により拡張した腸管から虚脱した腸管への移行部を見つけることができれば、そこが閉塞部位であり、腸閉塞/イレウスと診断されます。単純性腸閉塞の治療としては、絶飲食の上、経鼻胃管やイレウス管による腸内容物の吸引・減圧、輸液による脱水の改善と電解質補正、重症例での抗菌剤投与などの内科的治療をまず行います。内科的治療で改善しない単純性腸閉塞や複雑性(絞扼性)腸閉塞の治療として、腸管切除・吻合術などの外科的治療が行われます。麻痺性イレウスの治療は単純性腸閉塞の治療に準じ、内科的治療が行われます。
便秘症
便秘とは本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態であり、便秘症とは便秘による症状が現れ、検査や治療を必要とする状態と定義されています。
便秘の主な症状は、腹部の張る感じや、腹部不快感、重篤な場合では糞便がつまり、腸閉塞をきたし、激しい腹痛、発熱などを伴う場合があります。
便秘の原因としては、加齢、食習慣・運動習慣等の生活習慣、腸管の動きをおかしくするような糖尿病などの病気、大腸腫瘍、腹部手術の影響など様々なことが考えられ、便秘が頑固な場合や、便に血が混じる場合には、精査が必要となることもあります。
便秘の治療で一番大切なことは、日々の生活習慣を見直すことです。食事・運動・睡眠・ストレスなど、生活全般を見直して、お腹だけでなく体全体の調子を整えることは非常に大事です。生活習慣を整えても短期間では改善しないこともよくあります。そこで、効果的に便秘薬を用いて排便を整え、気持ちよく過ごせるようにしてきます。便秘の治療薬には、膨張性下剤、浸透圧性下剤(酸化マグネシウム、ポリエチレングリコール(モビコールⓇ)など)、刺激用下剤(センノシドなど)、上皮機能変容薬(ルビプロストン(アミティーザⓇ)、リナクロチド(リンゼスⓇ))、胆汁酸トランスポーター阻害薬(エロビキシバット(グーフィスⓇ))、漢方薬(大黄甘草湯など)などいくつかの種類の薬剤がありますので、お気軽にご相談ください。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群は、大腸や小腸に炎症や腫瘍などの器質的異常を認めないにもかかわらず、排便で軽快する腹痛や便通異常(下痢・便秘)といった症状が慢性的に持続する病気のことで、ストレスや社会環境を中心とした心理的要因が増悪因子として働くと考えられています。日本人の10〜20%にみられる頻度の高い疾患で、男性より女性に多く、20〜40歳代に多く見られます。便の性状により下痢型、便秘型、混合型(下痢と便秘を繰り返すタイプ)に分類され、男性は下痢型、女性は便秘型または混合型が多いと言われています。
過敏性腸症候群の治療としては、まずは規則正しい生活を心がけ、暴飲暴食を是正することにより排便リズムを整え、下痢型の場合は消化にいいものを、便秘型の場合は食物繊維が豊富な食べ物を摂取するようにすることから始めます。薬物療法としては、ポリカルボフィルカルシウム(便の水分量を調節する薬:ポリフルⓇ、コロネルⓇ)、トリメブチンマレイン酸塩(消化管運動調節薬:セレキノンⓇ)がまず用いられます。前記の薬で効果がみられないときには、下痢型の場合、塩酸ラモセトロン(セロトニン5-HT3 受容体拮抗薬:イリボーⓇ)、便秘型の場合、リナクロチド(リンゼスⓇ)が用いられ、奏功することがあります。
急性虫垂炎
急性虫垂炎とは、盲腸から突起状に垂れ下がった細長い器官である虫垂に生じた急性炎症のことで、虫垂の内腔が糞石(便が固まったもの)や食物残渣(食べかす)、リンパ組織の腫大、腫瘍などにより閉塞することにより内圧が上昇して、循環障害が生じ、二次的に細菌感染が加わることで発症します。急性腹症の中で最も頻度の高い疾患であり、10〜20歳代に好発します。
症状としては、初期には心窩部痛(みぞおちあたりの痛み)や臍周囲に鈍い周期性疼痛を自覚し、その後、右下腹部に限局する鋭い持続性疼痛を認めるようになります。発熱は軽度(37℃前後)ですが、穿孔(虫垂の壁に穴があくこと)をきたすと高熱(38℃以上)を呈し、腹痛部位の広がり、反跳痛(右下腹部を手で垂直に圧迫し、その手を急に離すときに感じる鋭い痛みのこと)などの腹膜刺激症状(腹膜に炎症が波及したときにみられる症状)を伴います。診断には血液検査と腹部CT検査などの画像検査が有用です。血液検査では炎症マーカー(白血球数、CRP)の上昇を認め、腹部CT検査では腫大した虫垂や嵌頓した糞石、周囲の滲出液を認めます。急性虫垂炎は上記の症状および血液検査結果やCT検査などの画像検査所見などによって診断されます。治療としては、腹膜刺激症状を欠く軽症例では抗菌薬投与による薬物療法が選択されることがありますが、軽症例でも再発する場合や中等症〜重症例では外科的治療(虫垂切除術)が選択されます。
大腸憩室症
大腸憩室とは大腸内圧の上昇により腸管壁の一部(粘膜および粘膜筋板)が腸管壁の圧力に弱い部位より小さな袋状に脱出したもののことであり、大腸に憩室がある状態を大腸憩室症と呼びます。日本人では右側結腸(上行結腸・横行結腸)に多くみられますが、加齢とともに左側結腸(S状結腸・下行結腸)にもみられるようになります。
一般に無症状ですが、大腸憩室炎や大腸憩室出血を併発すると次のような症状がみられます。大腸憩室炎では、強い腹痛、発熱、下痢などの症状を認めることがあり、大腸憩室出血の場合、腹痛を伴わない下血がみられ、大量下血となることもあります。腹部CT検査や大腸内視鏡検査にて大腸に憩室を確認できれば、大腸憩室症と診断されます。
大腸憩室炎や大腸憩室出血を併発せず症状がない場合は特別な治療は必要ありません。大腸憩室炎に対しては、抗菌薬投与による内科的治療が行われますが、膿瘍(膿がたまった空洞)や穿孔(大腸の壁に穴があくこと)を伴う場合や腸が狭くなっている場合には、外科的治療(大腸部分切除術)が選択されます。大腸憩室出血に対しては、安静の上、補液が行われますが、大量出血や持続的出血の場合、大腸内視鏡による止血術、血管造影下での塞栓術が実施されます。止血術が成功しない場合には外科的治療(大腸部分切除術)が選択されます。
肝障害
肝障害とは肝臓の機能が障害されている状態のことであり、血液検査の肝機能の項目(AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、γ-GTPなど)が高値を示していることにより指摘されることが多いです。肝障害には急性肝機能障害と慢性肝機能障害があります。急性肝機能障害の原因としては急性ウイルス性肝炎や薬剤の服用によって起こる薬物性肝障害などがあげられます。一方、慢性肝機能障害の原因としてはB型肝炎ウイルスによる慢性肝炎(B型慢性肝炎)やC型肝炎ウイルスによる慢性肝炎(C型慢性肝炎)、アルコールの長期摂取によるアルコール性肝障害、非アルコール性脂肪性肝疾患、自己免疫の異常による自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎などさまざまです。
肝臓は沈黙の臓器と呼ばれるように、初期の段階では、肝障害は無症状です。しかし、肝障害が慢性化すると、肝細胞が壊れ、そのあとに線維が沈着することにより肝臓が硬くなる肝硬変と呼ばれる状態となり、さらに肝機能が低下すると、肝不全と呼ばれる状態になります。肝不全まで進行すると黄疸(皮膚や目の白い部分が黄色くなる)やむくみ、腹水、全身倦怠感、意識障害などの症状が出現するようになります。肝硬変にまで進行すると、肝臓はもとの状態に戻ることはできず、肝がんを発症するリスクもあがりますので、健康診断などで肝障害を指摘された場合、放置せず、内科を受診されることをおすすめします。
診断としては血液検査と腹部超音波検査や腹部CT検査などの画像診断が有用です。血液検査では肝機能の項目(AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、γ-GTPなど)の上昇を認め、胆汁うっ滞がある場合には総ビリルビン(直接型優位)や胆道系酵素(γ-GTP、ALP)などの上昇も伴います。B型肝炎ウイルス/C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎が疑われる場合には、HBs抗原、HCV抗体を、自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎が疑われる場合には抗核抗体、抗ミトコンドリアM2抗体を測定します。画像検査では、肝障害をきたす原因疾患によって、それぞれ特徴的な所見が得られます。例えば、非アルコール性脂肪性肝疾患では腹部超音波検査において肝腎コントラスト、腹部CT検査において肝実質CT値の低下といった所見を認めます。肝障害は上記の症状および血液検査結果や腹部超音波検査や腹部CT検査などの画像検査所見などによって診断されます。
B型慢性肝炎やC型慢性肝炎の治療としては、抗ウイルス薬による治療が基本となります。アルコール性肝障害や非アルコール性脂肪性肝疾患の治療としては、禁酒、食事・運動療法が行われます。自己免疫性肝炎に対しては副腎皮質ステロイド薬が、原発性胆汁性胆管炎に対してはウルソデオキシコール酸やベザフィブラート(保険適用外)が治療薬として使用されます。
胆嚢炎・胆管炎
肝臓から十二指腸までの胆汁の通り道である胆道における感染症を胆道感染症といい、病変部位によって胆嚢炎と胆管炎に分類されます。胆道感染症は大腸菌、クレプシエラなどの細菌が腸管から胆道に逆行性に侵入、増殖することにより起こります。
急性胆嚢炎
急性胆嚢炎とは胆汁うっ滞に細菌感染症が加わることにより胆嚢に生じた急性炎症性疾患のことであり、多くは胆嚢結石が胆嚢管(胆嚢と総胆管をつなぐ短い管)を閉塞させることにより起こります。
症状としては右季肋部(右の肋骨の下あたり)痛、発熱、悪心・嘔吐などがみられます。診断としては血液検査と腹部超音波検査や腹部CT検査などの画像診断が有用です。血液検査では炎症マーカー(白血球数、CRP)の上昇を認め、胆汁うっ滞がある場合には総ビリルビン(直接型優位)や胆道系酵素(γ-GTP、ALP)などの上昇も伴います。腹部超音波検査や腹部CT検査では胆嚢腫大や胆泥(胆汁が異常に濃縮され、泥のようになったもの)、胆嚢壁の肥厚、胆嚢頸部にはまり込んでしまった胆嚢結石などを認めます。急性胆嚢炎は上記の症状および血液検査結果や腹部超音波検査や腹部CT検査などの画像検査所見などによって診断されます。
治療としては、原則として胆嚢摘出術を前提とし重症度に応じた治療が開始されます。初期治療としては、入院の上、絶食、輸液、抗菌薬・鎮痛薬投与などが行われ、可能な限り早期に腹腔鏡下胆嚢摘出術が実施されます。急性胆嚢炎が進行すると、胆嚢壁が穿孔(穴が開くこと)し、腹膜炎を併発するなど重症化することもありますので、初期治療が重要になります。
急性胆嚢炎と診断されましたら、速やかに連携先の地域基幹病院へご紹介させていただきます。
急性胆管炎
急性胆管炎とは胆管内に生じた急性炎症性疾患のことであり、総胆管結石や悪性腫瘍などにより胆管が閉塞し、胆汁がうっ滞することにより生じる細菌感染症です。胆汁うっ滞に より胆道内圧が上昇すると、大腸菌などの細菌やその細菌が壊れるなどして遊離することにより発熱物質として働くエンドトキシンが血中に移行しやすくなり、敗血症(細菌が増殖し、炎症を起こし、臓器障害まで引き起こしてしまう状態)をきたす可能性があります。敗血症はショックや意識障害、播種性血管内凝固(DIC:小さな血栓が全身の血管にできて、細い血管を詰まらせる病気)、急性腎不全などを合併することがあり、敗血症に至った急性胆管炎は緊急の胆道減圧を要する最重症の胆管炎で予後不良です。
症状としては高熱、右季肋部痛、黄疸がみられます。診断としては血液検査と腹部超音波検査や腹部CT検査などの画像診断が有用です。血液検査では炎症マーカー(白血球数、CRP)や総ビリルビン(直接型優位)、胆道系酵素(γ-GTP、ALP)などの上昇を認め、腹部超音波検査や腹部CT検査では拡張した胆管や総胆管結石などがみられます。急性胆管炎は上記の症状および血液検査結果や腹部超音波検査や腹部CT検査などの画像検査所見などによって診断されます。
治療としては、原則として胆道ドレナージ(溜まってしまった胆汁を外に排出する治療)を前提として重症度に応じた治療が開始されます。初期治療としては、入院の上、絶食、輸液、抗菌薬・鎮痛薬投与などが行われ、できるだけ早期に胆道ドレナージが実施されます。内視鏡的胆道ドレナージが第一選択となります。重症例ではショックやDICに対する治療も並行して行われます。
急性胆管炎と診断されましたら、速やかに連携先の地域基幹病院へご紹介させていただきます。
胆石症
胆石とは肝臓から十二指腸までの胆汁の通り道である胆道に形成された結石(脂肪を消化するために分泌される胆汁の成分が固まったもの)のことであり、成分によりコレステロール系結石(最多)、色素系結石、稀な結石に、部位により胆嚢結石(70〜80%)、総胆管結石(10〜20%)、肝内結石(1〜4%)にわけられます。中年以降、加齢とともに胆石保有率は高くなり、国内の胆石保有者は約5%です。
胆石症は胆道に結石ができてしまう病気のことであり、多くは無症状ですが、一般的な症状としては右季肋部(右の肋骨の下あたり)の激痛、右背部〜右肩への放散痛であり、食後に生じやすいのが特徴です。また、黄疸を発症したり、胆嚢炎や胆管炎を併発すれば発熱もみられます。
診断には血液検査と腹部超音波検査などの画像検査が有用です。血液検査では、総ビリルビン(直接型優位)や胆道系酵素(γ-GTP、ALP)の上昇などを認め、腹部超音波検査では、高エコーな胆石と胆石後方の音響陰影を認めます。胆石症は上記の症状および血液検査結果や腹部超音波検査などの画像検査所見などによって診断されます。
治療法は胆石の部位によって異なります。胆嚢結石の場合、無症状であれば経過観察とし、右季肋部痛を認める場合には、腹腔鏡下胆嚢摘出術が第一選択となります。総胆管結石の場合、症状の有無にかかわらず内視鏡的治療が原則であり、内視鏡的乳頭括約筋切開術( 胃内視鏡を十二指腸乳頭部まで挿入し、乳頭を切開・拡張した後に結石を除去する方法)が第一選択となります。肝内結石の場合、無症状であれば経過観察とし、症状を認める場合には、肝切除術や内視鏡的胆石摘出術などが行われます。
有症状の胆石症につきましては、速やかに連携先の地域基幹病院へご紹介させていただきます。
膵炎
膵炎とはさまざまな原因により膵臓に炎症が起きることで膵臓の組織が傷害される疾患のことであり、急性膵炎、慢性膵炎、自己免疫性膵炎に大別されます。
急性膵炎
急性膵炎とは何らかの原因により膵臓内で活性化されたアミラーゼなどの膵臓の消化酵素が膵臓および周囲の臓器を自己消化する急性炎症性疾患のことであり、中高年男性に多くみられます。原因としては男性ではアルコール多飲、女性では胆石によるものが多いですが、脂質異常症(高中性脂肪血症)、副甲状腺機能亢進症(高カルシウム血症)によって生じることもあります。重症度により軽症と重症に分類され、特に重症急性膵炎はショック、呼吸不全、急性腎不全などの多臓器不全をおこす死亡率の高い(約9.0%)危険な病気と言えます。
症状としては心窩部痛(みぞおちあたりの痛み)と背部痛、発熱、嘔気・嘔吐、食欲不振などがみられます。診断には血液検査と腹部CT検査などの画像検査が有用です。血液検査では、膵酵素(アミラーゼ、リパーゼなど)や炎症マーカー(白血球数、CRP)の上昇、腎機能の低下(尿素窒素およびクレアチニンの上昇)などを認め、腹部CT検査では、膵臓の腫大や、膵臓の輪郭不明瞭化、膵周囲の液体貯留などを認めます。急性膵炎は上記の症状および血液検査結果やCT検査などの画像検査所見などによって診断されます。
治療としては、入院の上、絶食および十分量の輸液に加え、タンパク分解酵素阻害薬や抗菌薬の点滴などが実施されます。重症例においては呼吸状態や血圧低下などに対する全身管理が必要となり、場合によっては、血液浄化療法も行われます。また、胆石性膵炎の場合、内視鏡治療による胆石除去が行われます。
急性膵炎が疑われ、入院が必要と考えられる場合には、速やかに連携先の地域基幹病院へご紹介させていただきます。
慢性膵炎
慢性膵炎とはアルコール多飲などが原因となり、膵臓が萎縮し、だんだんかたくなり(線維化)、石灰化を伴うなどの不可逆的な変化が膵臓に生じる病気のことであり、長期間のアルコール多飲歴のある中高年男性に多くみられます。原因としては、アルコール多飲によるものが約70%と多いですが、その他、特発性(原因が特定できない場合)、胆石によるもの、急性膵炎よりの移行によるものなどがあります。
症状としては、初期の段階(非代償期)では腹痛などの症状を繰り返しますが、進行すると(移行期)、膵外分泌機能(消化酵素を含む膵液をつくり分泌する機能)・内分泌機能(ホルモンをつくり分泌する機能)が低下する非代償期になると、脂肪便や下痢、体重減少、さらには膵性糖尿病(血糖値をさげるインスリンと血糖値を上げるグルカゴンの両方が欠乏する糖尿病)を発症することもあり、経過中に膵臓癌を発症するリスクも高くなります。
診断には血液検査と腹部CT検査などの画像検査が有用です。血液検査では、代償期〜移行期においては膵酵素(アミラーゼ、リパーゼなど)の上昇が認められるものの、非代償期になると、膵酵素は低下することが多いです。非代償期になり、膵性糖尿病を発症すると、血糖値やHbA1cの上昇、インスリン値の低下がみられます。腹部CT検査では、膵臓の萎縮や膵臓全体のびまん性石灰化、膵管内の結石(膵石)を認めます。慢性膵炎は上記の症状および血液検査結果やCT検査などの画像検査所見などによって診断されます。
治療としては、代償期〜移行期では禁酒、低脂質食などの生活指導の他、タンパク分解酵素阻害薬、鎮痛薬などの薬物療法を行います。非代償期になると、上記の生活指導の他、膵性糖尿病に対するインスリン頻回注射(1日4回のインスリン注射)や膵酵素補充療法を行います。
自己免疫性膵炎
自己免疫性膵炎とは発症に自己免疫機序の関与が疑われる、腹痛よりも黄疸が特徴的な膵炎のことであり、高齢男性に多くみられます。近年、全身性疾患(IgG4関連疾患)の膵病変であると考えられるようになっています。
自覚症状はなかなか現れずゆっくりと進行するため、黄疸や糖尿病症状で発症することが多いですが、軽度の腹痛や背部痛を呈することもあります。診断には血液検査と腹部CT検査などの画像検査が有用です。血液検査ではIgG4、総ビリルビン、γ-GTPなどの上昇がみられ、腹部CT検査ではびまん性(ソーセージ様)または限局性の膵腫大を認めます。自己免疫性膵炎は上記の症状および血液検査結果やCT検査などの画像検査所見などによって診断されます。治療としては、副腎皮質ステロイドによる薬物療法が第一選択です。少量のステロイド薬を継続内服することによって普段どおりの生活を送ることが可能とされています。
尿路感染症
尿路感染症とは尿の通り道に細菌が入る病気を言います。細菌がはいった場所によって、尿道炎、膀胱炎、腎盂腎炎などに分類します。細菌が入れば、入った場所ごとに調子が悪くなるわけですが、症状がないことも珍しくありません。特に高齢になるにしたがって、いつも膀胱内に細菌がいる人が増えます。このような状態は無症候性慢性膀胱炎とか無症候性細菌尿などといいます。
尿道炎では頻尿や排尿時痛など、膀胱炎では頻尿や排尿時痛、残尿感、血尿など、腎盂腎炎では発熱(高熱)や片側の側腹部痛、腰痛などの症状がみられます。
治療としては、抗生剤治療が基本となります。
尿路結石症
尿路結石症とは腎臓から尿道にいたる尿路(尿の通り道)に結石(尿成分のカルシウム、シュウ酸、リン酸、尿酸などが析出・結晶化し、これらが集合・沈着・増大して、尿路内にとどまったもの)ができる疾患のことです。尿管結石はできる場所によって上部尿管結石(腎結石・尿管結石)と下部尿管結石(膀胱結石・尿道結石・前立腺結石)に分けられますが、上部尿管結石が96%を占め、下部尿管結石は4%にすぎません。脱水症をおこしやすい夏季に発症することが多く、典型的な症状としては血尿、疝痛発作(突然の激しい痛み)があげられます。疝痛については、尿管に結石がつまることにより、尿が流れなくなったり、逆流したりして、尿管や腎臓を圧迫することにより生じると考えられています。
上部尿管結石の診断には腹部CT検査が有用です。問診や診察にて上部尿管結石が疑われた場合、尿検査にて顕微鏡的血尿(尿潜血陽性)もしくは肉眼的血尿を確認の上、腹部CT検査にて尿管内の結石および結石より上流の尿管・腎盂・腎杯の拡張(水尿管症、水腎症)などが見られると、尿管結石症と診断されます。治療としては、痛み止め(非ステロイド性抗炎症薬)の内服、坐薬による治療をまず行い、10 mm未満の結石は自然排石(結石が尿と一緒に出てくる)することが多いため、飲水(2〜3 L/日)を促し、場合によっては排石促進剤を使用します。10 mm以上の結石に対しては、体外衝撃波結石破砕術(ESWL)や内視鏡的治療である経尿道的尿路結石破砕術(TUL)、経皮的腎結石破砕術(PNL)が実施されます。
蕁麻疹(じんましん)
じんましんは皮膚の一部が突然くっきりと赤く盛り上がり(膨疹)、しばらくすると跡形もなくかゆみと皮疹が消えるという特徴があります。たいていかゆみを伴いますが、チクチクとした感じや焼けるような感じになることもあります。発症して6週間以内を「急性じんましん」、それ以上経過した場合を「慢性じんましん」と呼びます。じんましんの治療は、まず原因や悪化因子を探して、それらを取り除く、または避けるようにすることです。アレルギーが原因であれば、原因アレルゲンや刺激を回避します。仕事や勉強などのストレスや不規則な生活を避けることも重要です。薬物治療は、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬などの飲み薬や塗り薬が中心となります
アレルギー性鼻炎(季節性(花粉症)・通年性)
アレルギー性鼻炎には、スギ花粉やヒノキ花粉などが原因で起こる「季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)」と、ダニやほこり(ハウスダスト)などが原因で季節に関係なく起こる「通年性アレルギー性鼻炎」があります。さらっとした透明の鼻水、鼻づまり(鼻閉)、発作的に起こる連発するくしゃみが主な症状で、空気中に浮遊する原因物質(アレルゲン)が鼻の粘膜から体内に入ることによって起こります。
アレルギー性鼻炎の治療には「薬物療法」、「アレルゲン免疫療法」、「手術療法」があります。また、症状の原因となるスギ花粉やダニ、ほこり(ハウスダスト)などのアレルゲンを回避する環境を整えることも重要です。
薬物療法では鼻水やくしゃみをおさえる抗ヒスタミン薬(ヒスタミンH1受容体拮抗薬)や鼻づまりを改善する作用があるロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)、鼻の炎症をおさえる点噴霧用鼻ステロイド薬などが用いられます。抗ヒスタミン薬の副作用として眠気があげられますが、眠気を引き起こすのはほとんどが第一世代の抗ヒスタミン薬で、第二世代の抗ヒスタミン薬は脳内移行が少ないため、眠気がおこりにくいと考えられています。
アレルゲン免疫療法は、原因となるアレルゲンを繰り返し投与し、体をアレルゲンに慣らしながら、体のアレルギー反応を弱める治療法です。アレルゲン免疫療法には注射でアレルゲンを投与する皮下免疫療法と舌下錠でアレルゲンを投与する舌下免疫療法があります。現在、日本ではダニとスギ花粉に対する舌下免疫療法を受けることができ、当院でもダニとスギ花粉に対する舌下免疫療法を受けていただくことが可能です。効果発現までに数ヶ月〜1年、治療全体として3〜5年の期間を要しますが、薬物療法だけでは症状がおさえられないような患者さまや副作用のため薬物療法を継続できない患者さまではアレルゲン免疫療法が考慮されます。
手術療法には鼻の粘膜をラジオ波で焼灼する下鼻甲介粘膜焼灼術やくしゃみ・鼻水を引き起こす後鼻神経を下鼻甲介の後方で焼灼・切断する後鼻神経切断術などがあります。薬物療法でも症状がおさえられない場合などに考慮される治療です。
頭痛
頭痛とは頭部や後頸部の一部あるいは全体の痛みのことであり、我が国の人口の約3人に1人(約4,000万人)は頭痛を患っていると言われています。明らかな基礎疾患がないにもかかわらず、頻繁に起こる頭痛を一次性頭痛(慢性頭痛)といい、何らかの脳や頭部などの疾患のために発生する頭痛を二次性頭痛(症候性頭痛)といいます。一次性頭痛が直接生命に関わらない頭痛であるのに対して、二次性頭痛は緊急性が高く、直接生命に関わることがある頭痛です。
頭痛の診断においては、まず始めに一次性頭痛と二次性頭痛の鑑別を行います。二次性頭痛の中には生命に関わる危険な頭痛もあるため、まず二次性頭痛の可能性を除外することが重要です。二次性頭痛の代表的な原因疾患としては、クモ膜下出血や脳出血などの脳血管障害と脳腫瘍などがあげられ、その他、むち打ちによる持続性頭痛、薬物乱用頭痛、髄膜炎による頭痛、高山性頭痛、急性副鼻腔炎による頭痛、精神疾患による頭痛なども二次性頭痛に含まれます。二次性頭痛の除外診断には、頭部CT検査が有用です。急に発症した、これまでに経験したことのないような激しい頭痛を自覚し、手足の麻痺やしびれ、ろれつが回らないなどの症状を伴うような場合には、脳血管障害が疑われるため、至急、基幹病院の脳卒中センターなどを受診されることをおすすめします。また、朝起床時に頭痛を感じるようになり、頭痛の悪化に伴い、嘔気・嘔吐も認め、やがて終日、頭痛を感じるようになった場合、脳腫瘍による頭痛が疑われますので、至急、頭部CT検査を受けられることをおすすめします。頭部CT検査などの画像検査にて二次性頭痛が除外されると、一次性頭痛が疑われます。一次性頭痛には多くの種類がありますが、主なものは片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛の3つです。
片頭痛
片頭痛は主にこめかみから側頭部にかけて生じる拍動性で中等度〜重度の頭痛です。正確な機序は明らかではありませんが、脳血管を取り巻く三叉神経の興奮や脳血管の拡張が関与していると考えられています。20〜40歳代の女性に多くみられ、頭痛の前に視野にキザギザした光がちらつく(閃輝暗点)などの前兆がある場合(約30%)とない場合(約70%)があります。こめかみから側頭部にかけてズキンズキンとした脈打つような頭痛が4〜72時間持続し、この発作が1ヶ月に1〜5回程度繰り返されるようになります。歩行、階段昇降、家事などの日常動作によって頭痛が増悪するのが特徴で、頭痛時、光や音、臭いに過敏となり、悪心・嘔吐を伴うことがあります。片頭痛の診断は意外に容易ではなく、頭部CT検査や頭部MRI検査にて二次性頭痛が除外された上で、問診において前記の片頭痛の特徴と合致する点が多い場合、片頭痛の可能性が高くなります。片頭痛治療薬が奏功すれば、ようやく片頭痛と診断できるといった具合です。片頭痛の治療は、発作時と非発作時(予防)に分けられます。発作時には、トリプタン製剤や鎮痛薬(非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、アセトアミノフェン)、制吐薬などが使用され、歩行や階段昇降などの増悪因子を避け、暗く静かな場所で安静にするようにします。片頭痛の発作が月に2回以上、あるいは生活に支障をきたす頭痛が月に3日以上ある患者さんにおいては、非発作時の治療(予防治療)を検討することがすすめられています。予防治療薬としてはカルシウム拮抗薬(ロメリジン)、抗てんかん薬(バルプロ酸)、β遮断薬(プロプラノロール)、抗うつ薬(アミトリプチリン)などが使用されます。また、最近、カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)が片頭痛の病態に関与していることがわかり、片頭痛の予防注射薬として、CGRPやCGRP受容体に対するモノクローナル抗体(抗CGRP抗体/抗CGRP受容体抗体)が2021年より保険適用となっています。
緊張型頭痛
緊張型頭痛は主に頭頂部から後頭部の筋緊張により生じる非拍動性で軽度〜中等度の頭痛です。一次性頭痛の中で最も多く、30〜50歳代の女性に多くみられ、頭痛患者の約半数を占めるといわれています。頭を締め付けるような頭痛(後頭部周囲が多い)や頭重感が終日持続し、夕方強くなる傾向があります。痛みの程度は軽度〜中等度で、肩こりを伴うことが多く、日常動作によって増悪せず、光・音過敏や悪心・嘔吐を伴うことはほとんどありません。緊張型頭痛は様々な誘因によって、頭部を支える頭頂部〜後頭部の筋肉の緊張(こり)が生じ、頭痛になると考えられており、パソコンやスマホを長時間、同じ姿勢で操作されていられる方によくみられます。診断としては、頭部CT検査や頭部MRI検査にて二次性頭痛が除外された上で、問診において前記の緊張型頭痛の特徴と合致する点が多い場合、緊張型頭痛と診断されます。治療としては、頭痛体操(頭頂部〜後頭部の筋肉のストレッチ体操)などのストレッチを実施しつつ、鎮痛薬(非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、アセトアミノフェン)、抗不安薬、筋弛緩薬などが使用されます。
群発頭痛
群発頭痛は片側の眼窩部〜側頭部にかけてえぐられるような激痛発作を生じる頭痛です。一次性頭痛の中で最も痛みが激しい頭痛で、20〜40歳代の男性に多くみられ、大酒家、ヘビースモーカー、不規則な睡眠サイクルの人に多いといわれています。主に深夜、突然片側の眼窩部のえぐられるような重度〜極めて重度の激痛が1時間ほど持続し、頭痛発作中に流涙、結膜充血、鼻閉、鼻漏などの症状を伴うことが多いです。およそ1ヶ月間、毎日同じような時間帯に頭痛発作が出現します。片頭痛やクモ膜下出血などでは、頭痛のために身動きできないことが多いのに対して、群発頭痛では激痛のため、のたうち回る、動き回る、頭を叩くなどの行動を伴いやすいです。診断としては、頭部CT検査や頭部MRI検査にて二次性頭痛が除外された上で、問診において前記の群発頭痛の特徴と合致する点が多い場合、群発頭痛と診断されます。治療としては、まずは規則正しい睡眠、禁煙、アルコール摂取制限などの生活習慣改善を行い、急性期治療(発作時の治療)としてトリプタン製剤(皮下注射)、100%酸素吸入などを行うとともに、予防治療(非発作時の治療)としてカルシウム拮抗薬(ベラパミル)やステロイド(プレドニゾロン)などが使用されます。
生活習慣病
生活習慣病は、食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関与し、それらが発症の要因となる疾患の総称です。日本人の三大死因である、がん、心疾患、脳血管疾患や、これらの疾患の危険因子となる糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、肥満症などはいずれも生活習慣病とされています。生活習慣病の多くは自覚症状のないまま進行していきます。そのため、日ごろから特定健診をはじめとする各種健診を受けて体の変化を確認し、病気になる前に生活習慣を見直しましょう。検査値に異常がある場合や少しでも不安を持たれた時は、お早めにご相談ください。
糖尿病
糖尿病とは膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが、十分に働かないために血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高くなる病気です。大きく1型糖尿病と2型糖尿病に分かれており、日本人で圧倒的に多く、生活習慣病の一つとされているのが2型糖尿病です。その発症には、インスリンの分泌不足といった要因に加え、過食、運動不足、肥満、ストレスといった生活習慣が関係しているといわれています。
糖尿病を発症し進行すると、神経障害、網膜症、腎症など様々な合併症を引き起こすことがあります。糖尿病を予防するため、あるいは進行を遅らせるために生活習慣を見直すことが大切です。当院では諸検査の結果に基づき、患者さま一人ひとりのライフスタイルに応じたきめ細かな治療を行っています。
高血圧症
日本高血圧学会では上の血圧である収縮期血圧(心臓が収縮したときの血圧)が140mmHg以上、または下の血圧である拡張期血圧(拡張したときの血圧)が90mmHg以上を高血圧症としています。そのまま高血圧の状態にしておくと脳や心臓の血管が動脈硬化を起こし、脳卒中や心臓病、腎臓病などの重大な病気を発症する危険性が高まります。日本人の高血圧症の約8~9割が本態性高血圧症(原因をひとつに定めることのできない高血圧症)で、遺伝的素因(体質)や食塩の過剰摂取、肥満など様々な要因が組み合わさって発症します。中年以降にみられ、食生活を中心とした生活習慣の改善が予防・治療に非常に大切です。
脂質異常症
脂質異常症とは血液中の「悪玉」と呼ばれるLDLコレステロールや中性脂肪(トリグリセリド)が増えたり、「善玉」のHDLコレステロールが減ったりした状態のことをいいます。この状態を放置していると動脈硬化が起こり、ゆっくり進行し、脳梗塞や心筋梗塞といった動脈硬化性疾患をまねくリスクが高まります。
脂質異常症の発症には、過食、運動不足、肥満、喫煙、過度な飲酒、ストレスなどが関係しているといわれています。
脂質異常症の治療は通常、食事療法と運動療法からはじめます。薬物療法は、これらを行っても脂質管理の目標値が達成できなかったり、持っている動脈硬化の危険因子が多く、動脈硬化や動脈硬化による疾患を起こすリスクが高かったりする場合に開始されます。
高尿酸血症
高尿酸血症とは、血液中の尿酸の濃度(尿酸値)が通常よりも高い状態のことです。高尿酸血症には、尿酸の排泄がうまくいかないタイプ・体内で尿酸をつくりすぎるタイプ・両者の混合型の3つがあり、日本人には排泄がうまくいかないタイプが多いとされています。女性ホルモンには腎臓からの尿酸の排泄を促す作用があるため、明らかな性差が認められ患者さまの大半が男性です。
尿酸が過剰になると、体内で析出して結晶を作り、痛風と呼ばれる病気を発症することがあります。尿酸の結晶は足の親指の付け根に形成されることが多く、激烈な痛みや発赤、腫れなどの痛風関節炎(痛風発作)を引き起こします。そのほか、腎臓にも結晶を作ることもあり、腎臓結石の原因にもなります。高尿酸血症は、アルコールや肉を多く摂取する、といった生活習慣と密接に関連していると考えられています。こうした生活スタイルは、糖尿病や高血圧、脂質異常症、肥満などとも関連しており、動脈硬化を進行させないという観点からも治療を行う必要があります。
糖尿病・内分泌(甲状腺)のご相談は大阪市西区のきよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニックへ
大阪市中央区や大阪市西区で糖尿病や甲状腺疾患についてご相談をお考えの方は、肥後橋駅徒歩1分、淀屋橋駅からも徒歩6分の「きよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニック」にお問い合わせください。専門医による診療とアクセスの良さが特徴です。
当院では、糖尿病・内分泌疾患を専門とする医師による診療が行われており、糖尿病や甲状腺疾患をはじめとするさまざまな内分泌・代謝疾患の診断と治療に対応しています。特に甲状腺の異常や糖尿病に関連する検査に対応するための設備を整えております。まず初めに、糖尿病・内分泌領域の専門医が詳細な問診や診察をさせていただきます。その後、当院導入の大型血液検査装置や超音波検査装置、CT検査装置設備などを活用し、患者さまの症状に応じた適切な検査を受けていただくことが可能です。検査の結果は患者さまに丁寧に説明させていただき、その結果に基づいて、できるかぎり患者さまの意向に沿った治療方針をご提案いたします。
また、夜間診療も実施しており、仕事帰りにも通院しやすい診療体制を整え、患者さまの健康状態やご要望に合わせた診療を心がけております。予約は電話やオンラインから可能です。予約をご利用いただくことで、診療がより円滑に進められます。大阪市で内科診療をご希望の方は、「きよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニック」にご相談ください。尚、診療内容の詳細については直接お問い合わせください。
監修者情報
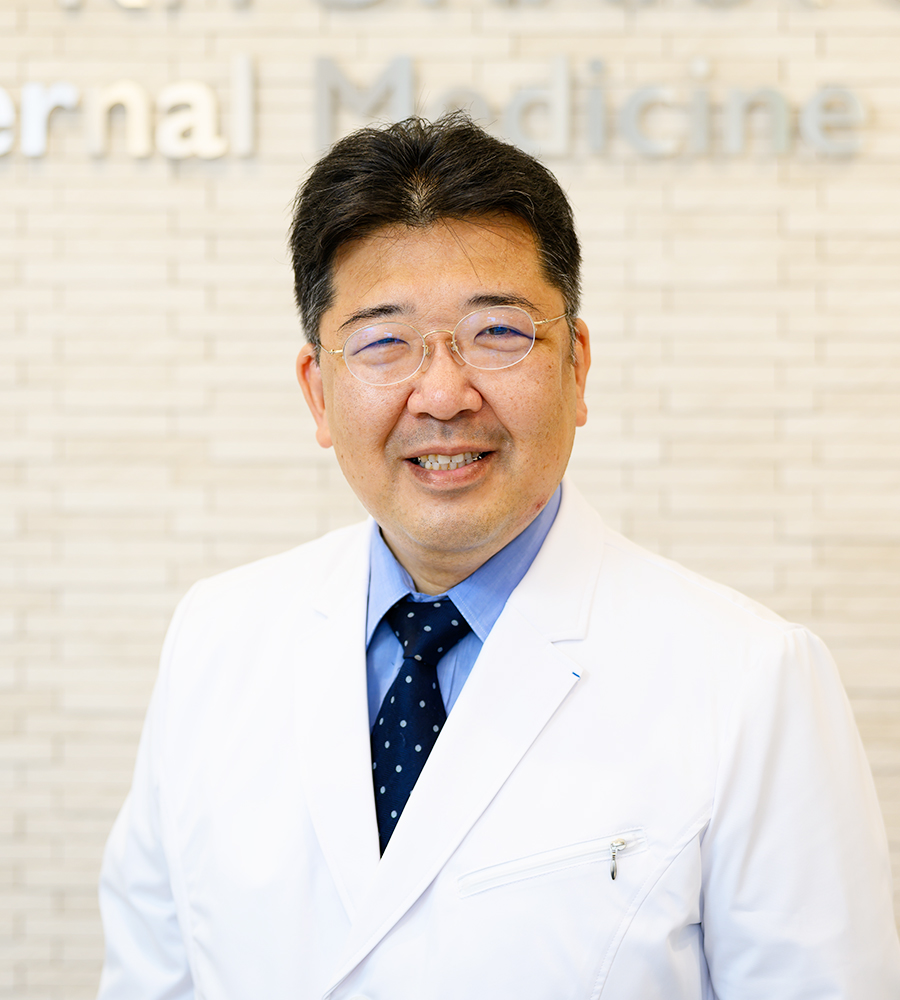
清原 義幹(きよはら よしもと)
きよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニック 院長
経歴
- 1997年神戸大学医学部附属病院 内科系 研修医
- 1998年京都大学大学院医学研究科 博士課程入学
- 2003年京都大学大学院医学研究科 博士課程修了
- 2003年独立行政法人理化学研究所 研究員
- 2007年INSERM フランス国立医学研究機構 研究員
- 2008年医療法人浩仁会 南堺病院 内科 医員
- 2010年医療法人浩仁会 南堺病院 内科 医長
- 2012年独立行政法人労働者健康福祉機構 大阪労災病院 糖尿病内科 医長
- 2016年独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 糖尿病内科 医長
- 2018年独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 糖尿病内科 副部長
- 2019年医療法人浩仁会 南堺病院 糖尿病内科 部長
- 2024年きよはら内科クリニック(現:きよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニック) 院長
ご挨拶
大阪市西区・肥後橋のきよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニックの清原義幹です。当院は糖尿病内科、内分泌 (甲状腺)・代謝内科を中心とした内科専門クリニックです。総合内科・糖尿病・内分泌代謝科の専門医としての知識と経験を活かしつつ、一般内科全般から糖尿病や甲状腺疾患をはじめとする内分泌疾患、高尿酸血症(痛風)などの代謝疾患、健康診断、予防接種まで幅広く診療しております。些細なことであっても、お身体のことでお困りのことがございましたら、是非お気軽にご相談ください。
