- HOME>
- せき・たん・呼吸苦・鼻水
長引く咳
長引く咳

咳は気道内に侵入してきた異物(ほこり・ウイルス・細菌など)を排出するために起こる生体防御反応です。ウイルス性のかぜを引いたときに鼻汁やのどの痛みなどと一緒に咳を経験しますが、この場合、十分な栄養や睡眠をとって静養すれば、免疫機能が働き多くは3週間以内に治まります。細菌によるかぜは、ウイルス性のふつうのかぜに比べて症状が重くなることもありますが、抗生物質を使うことで速やかな治療が可能です。
3週間以上続く場合や1週目でも数日間眠れないほど激しい咳が続く場合は、ただのかぜではなく、他の病気が原因になっている可能性があります。咳は原因を特定した上で治療を行うことが大切なため、長引く咳は早めの受診をお勧めします。
「長引く咳」が現れる主な病気
長引く咳の診断は、喘鳴(ぜんめい:ゼーゼー、ヒューヒューという音)が認められるか、痰が出ているか、ということがポイントとなります。さらに詳細な問診やⅩ線検査などを組み合わせて鑑別していきます。
また、胃食道逆流症(逆流性食道炎)で酸の逆流の刺激によって咳が出たり、精神的ストレス(心因性咳嗽⦅がいそう⦆)や降圧薬などの副作用としても咳症状が認められたりすることがあります。
気管支喘息(喘息)
気管支喘息は気道(口や鼻から肺につながる空気の通り道)に炎症が続き、さまざまな刺激に気道が敏感となり発作的に気道が狭くなることを繰り返す病気です。このため咳や痰が出て、ゼーゼー、ヒューヒューという音(喘鳴)を伴って息苦しくなり(呼吸困難)、命に関わることもあります。夜間や早朝に症状が出やすいのが特徴です。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
慢性閉塞性肺疾患(COPD)とは、慢性気管支炎や肺気腫などの病気の総称です。主な原因はタバコや加齢といわれています。気管支の炎症や肺の弾性の低下が起こり、呼吸をするときに酸素を失った空気が肺に残ることによって、酸素の多い新鮮な空気を吸い込むことができず息苦しいといった症状が長期にわたり続きます。
早期に診断を受けて治療を開始すれば、呼吸機能の低下を食い止められ、健康な人と変わらない生活を続けることができます。少しでも軽症のうちに発見して治療をはじめることが重要といえます。
副鼻腔炎
急性副鼻腔炎
ウイルスや細菌が副鼻腔に感染する病気です。かぜをひいた後に生じることが多く、かぜに続いて細菌感染が副鼻腔にもたらされて起こります。膿のような鼻汁が出て、限られた空間に膿がたまるため、頬や目の奥が痛みます。
慢性副鼻腔炎(蓄膿症)
絶えず鼻水が出る、常に鼻がつまり口で呼吸をしている、においを感じにくい、いびきをかくといった症状があります。治療は鼻内の清掃、副鼻腔の鼻処置と、抗生剤や去痰剤、抗アレルギー剤などによる薬物療法を行います。比較的長期にマクロライド系の抗生剤の内服を行いますが、治らない場合は手術が検討されることもあります。
胃食道逆流症(逆流性食道炎)
強い酸性の胃液(胃酸)が胃の内容物とともに食道に逆流し、食道の粘膜に炎症が生じる病気です。胃酸が増え過ぎてしまったり、胃酸の逆流を防ぐ機能がうまく働かなかったりすることで起こります。胃酸がのどまで上がってきて酸っぱいと感じるようになったり、胸やけやのどがヒリヒリしたりして不快感が続きます。喫煙、飲酒などの生活習慣や加齢、肥満、姿勢、食道裂孔ヘルニアなどが原因となります。
食道や胃といった消化器の疾患と、咳症状の関連性について不思議に思われる方も多いでしょう。原因は逆流した胃酸です。この胃酸がのどや気管支を刺激したり、食道粘膜を通して神経を刺激したりすることで、空咳や声がれの症状を起こします。ただ、現れ方はそれぞれで、消化器系の症状だけの方、咳や声がれの症状だけの方、両方の症状が出る方もいらっしゃいます。
せき喘息
長引く咳の原因として多いのが「せき喘息」です。痰が出ない乾いた咳が続くのが特徴で、気管支喘息特有の喘鳴や呼吸困難はありません。せき喘息は気管支喘息ではありませんが、気管支喘息と同様に気道に炎症が起こり、様々な刺激によって気道が狭くなり咳が出ます。アレルギー体質の方に多くみられ、ダニやホコリなどのアレルゲンが咳発作を誘発したり、早朝や深夜、季節の変わり目などに症状が出たりすることが多いといわれています。
治療せずに放置すると、気管支喘息に移行してしまうこともあります。喘鳴のない乾いた咳が8週間以上続く場合、せき喘息の可能性もありますので、早めの受診をお勧めします。
鼻の症状
鼻は呼吸や嗅覚、声の共鳴に関わる大切な器官です。
鼻に起こる症状には、鼻炎、副鼻腔炎、後鼻漏、嗅覚障害などがあります。
おもな症状
- 鼻水がでる
- 鼻水に悪臭がある
- 鼻詰まりがひどい
- 鼻水がのどに落ちる感じ
- 鼻血がよくでる
- いびきがひどい
- 鼻の奥が痛い
- においを感じないなど
鼻の主な病気
鼻炎
鼻の粘膜に発生した、急性または慢性の炎症のことです。
放置すると慢性鼻炎や副鼻腔炎に移行することもありますので、長引く場合は、放置せずに、お早めに当院にご相談ください。
副鼻腔炎(蓄膿症)
副鼻腔とは、鼻と口とを繋ぐトンネルの部分です。そこに炎症が起きる病気が副鼻腔炎です。慢性の副鼻腔炎は、蓄膿症と呼ばれることもあります。
炎症により発生した膿が鼻腔から細い筒状のトンネル(自然孔)から排泄されずに溜まって慢性化します。
後鼻漏
後鼻漏(こうびろう)は、鼻水がノドの方へ流れ落ちてくる症状です。
かぜやアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎などで、鼻内の鼻水が増えてくると、のどに落ちていく後鼻漏が普段よりも増えてきて、それがのどの違和感、咳の原因になります。また鼻の奥には咽頭扁桃と呼ばれるリンパ組織があります。ここのリンパ組織に炎症が生じると、リンパ組織が赤く腫れて、分泌液が増えます。そのため、鼻汁がのどに落ちるようなのどの違和感が生じることがあります。胃酸逆流による刺激でリンパ組織に炎症が生じる場合もあります。
嗅覚障害
においの感覚に何らかの異常をきたす症状で「嗅覚異常」とも言われています。
嗅覚障害は風邪やインフルエンザなどの呼吸器系感染症や、花粉症など鼻炎・副鼻腔炎を原因として発生することがあります。
監修者情報
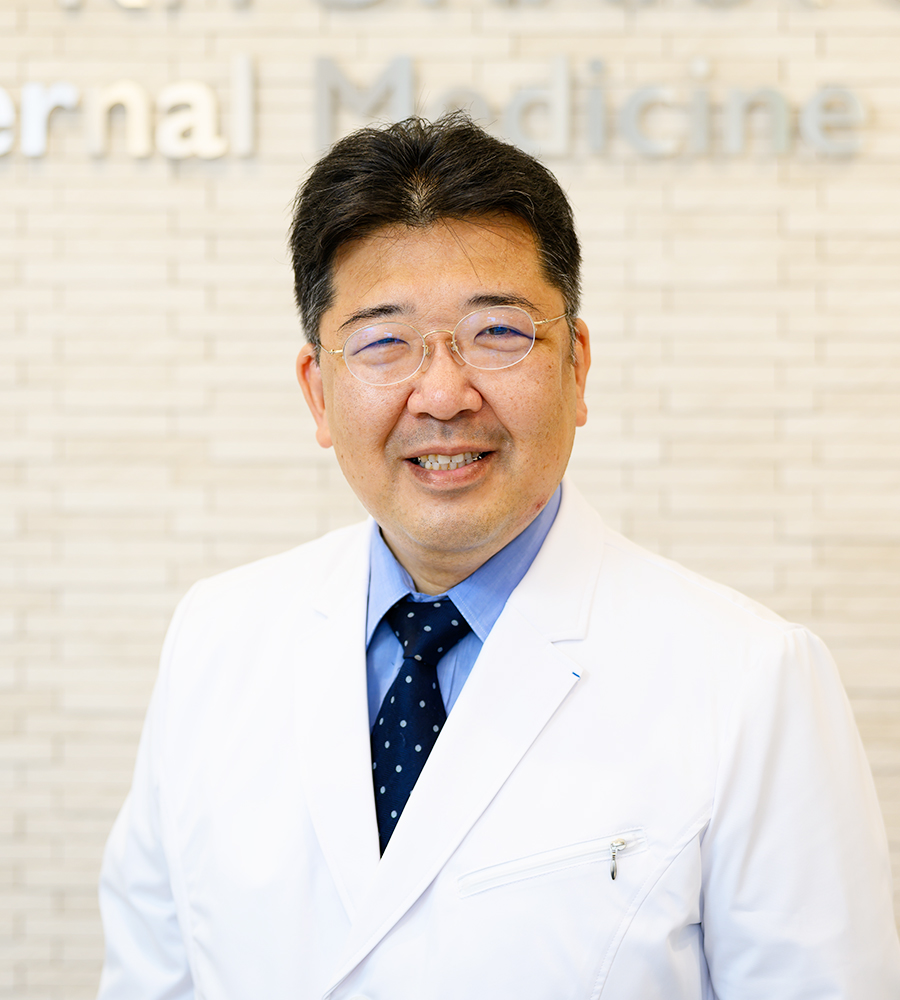
清原 義幹(きよはら よしもと)
きよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニック 院長
経歴
- 1997年神戸大学医学部附属病院 内科系 研修医
- 1998年京都大学大学院医学研究科 博士課程入学
- 2003年京都大学大学院医学研究科 博士課程修了
- 2003年独立行政法人理化学研究所 研究員
- 2007年INSERM フランス国立医学研究機構 研究員
- 2008年医療法人浩仁会 南堺病院 内科 医員
- 2010年医療法人浩仁会 南堺病院 内科 医長
- 2012年独立行政法人労働者健康福祉機構 大阪労災病院 糖尿病内科 医長
- 2016年独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 糖尿病内科 医長
- 2018年独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 糖尿病内科 副部長
- 2019年医療法人浩仁会 南堺病院 糖尿病内科 部長
- 2024年きよはら内科クリニック(現:きよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニック) 院長
ご挨拶
大阪市西区・肥後橋のきよはら内科 糖尿病・甲状腺クリニックの清原義幹です。当院は糖尿病内科、内分泌 (甲状腺)・代謝内科を中心とした内科専門クリニックです。総合内科・糖尿病・内分泌代謝科の専門医としての知識と経験を活かしつつ、一般内科全般から糖尿病や甲状腺疾患をはじめとする内分泌疾患、高尿酸血症(痛風)などの代謝疾患、健康診断、予防接種まで幅広く診療しております。些細なことであっても、お身体のことでお困りのことがございましたら、是非お気軽にご相談ください。
